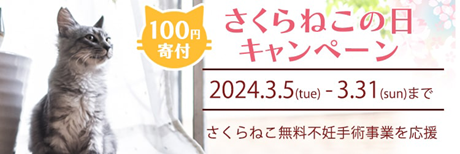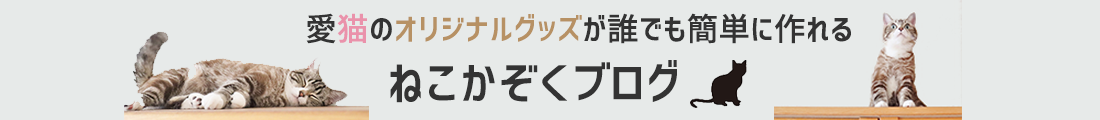
ねこを飼うなら知っておきたい、飼育書には書かれていない大切なこと

ねこと暮らしはじめて「こんなはずでは…」となるのはとっても悲しいですよね。
そうならないためには、ねこの習性や行動について知り、快適な室内環境を提供することが重要です。
そこで今回はねこの行動、習性、部屋の環境作りに重点をおいて、ねこを飼う前に知っておきたいことをまとめました。
目次
1.飼う前に知っておきたいねこの習性と行動
∟1-1.ねこは単独行動を好む
∟1-2.ねこは高い場所が好き
∟1-3.ねこは好みにうるさい
∟1-4.ねこは夜中に突然走り出すことがある
∟1-5.狩猟本能は消えない
∟1-6.爪とぎはやめさせられない
2.ねこを迎えるための環境づくり
∟2-1.面積よりも高さが重要
∟2-2.ねこと暮らすために必要な面積は?
∟2-3.模様替えはストレスのもと
∟2-4.ものは片付ける・飾らない
∟2-5.室内にはねこにとって危険なものがいっぱい
∟2-6.自宅の脱走防止対策を徹底する
3.猫の飼育費用
まとめ
1.飼う前に知っておきたいねこの習性と行動

実際にねこと暮らしている人たちのあいだで聞かれる、ねこの驚きの習性やねこあるあるな行動をもとに、ねこと暮らすとこんなことが起こるよ、こんな行動をするよ、ということをまとめました。
1-1.ねこは単独行動を好む
ねこを多頭飼いしている飼い主さんは多くいらっしゃいますが、実はねこは多頭飼いには向いていません。
と言うのは、ねこは縄張り意識が強く、単独行動を好む動物だからです。
いぬのように群れを作らないこともあって、どちらかというと社会性が低いと考えられています。
ただし、自分にとってメリットがあると判断できた場合には、ほかのねことも同居は可能です。
とくに、血縁関係にあるねこや子猫のころからいっしょに過ごしているねこ(ほかの動物や人間も同様です)といった信頼できる相手とならば、よい関係を築くことができるでしょう。
大人になってからでも、食べ物が十分にあり、安心して眠ることのできる場所が確保できさえすれば大丈夫な場合もあります。
とは言え、多頭飼いを考えるなら兄弟猫を引き取る、あるいは子猫のうちからいっしょに飼いはじめるのがよいでしょう。
1-2.ねこは高い場所が好き
ねこは高い場所に登るのが大好きです。その主な理由は3つあります。
- ・外敵に遭遇する可能性が低く、襲われる心配がない
- ・周りを見渡せるので身の安全を確保できる
- ・ほかの動物に対して自分が優位だと主張できる
高い場所は大型の肉食獣が登ってきにくく、外敵の接近に気づきやすいため、ねこにとっては身を守るのに適しています。
また、縄張りを共有するほかのねこに対して、自分のほうが強いことをアピールする意味合いもあると言われています。
そのほか、ノミ・ダニなどの害虫が少ないこと、飼いねこの場合は運動のためという理由もあるようです。
ねこが高い場所で生活するよう進化していきましたので、高い場所を好むのは本能的な行動でもあります。
キャットタワーなどを用意し、安全に登れる場所を用意してあげるのがいいでしょう。
1-3.ねこは好みにうるさい
ねこは、好き嫌いがはっきりしている動物です。
せっかく用意したベッドも気に入らなければ使いません。
トイレも気に入らなければ使わなかったり、好きではないと主張したりします。
おもちゃも好みに合わなければ見向きもしません。
食べ物でさえ、嫌いなものはどれだけお腹が空いていてもいっさい手をつけないというねこもいるほどです。
つまり、好きか嫌いかがすべてなのです。あなたがどれほど愛猫のことを思って選んだかなどは忖度しません。むしろ、飼い主をがっかりさせる名手なのだということを覚えておきましょう。
1-4.ねこは夜中に突然走り出すことがある
ねこは夜中になんの前触れもなく部屋の中を走りまわることがあります。飼い主さんたちのあいだでは「夜の運動会」「真夜中の大運動会」などと呼ばれています。
遊び足りなかったときの運動不足を解消するため、欲求不満やストレスを発散するための行動だとも考えられています。
こうした行動のせいで飼い主さんが睡眠不足になったり、近所から苦情が来たりすることもあります。
そうならないためにも、日ごろから十分に運動させ、ストレスを溜めないようにしてあげるのがよいでしょう。
1-5.狩猟本能は消えない
もともと狩りをして暮らしていたねこには、今でも狩猟本能が残っています。人間と暮らしていて食べ物が十分に得られる飼いねこも例外ではありません。
おもちゃで遊んでいると、前足で押さえつける、後ろ足で蹴る、噛むといった狩りに直結する行動が見られます。
実際に狩りをした経験がないねこでも、本能的に狩りをしているのです。
この本能が、飼い主さんやその家族、あるいは同居しているほかの動物に向けられると厄介なことになります。
ねこには鋭い牙と爪があるので、本気で飛びかかってくると大怪我をする原因にもなりかねません。
手や指でねこを遊ばせてはいけないと言われるのはそのためです。
ねこを遊ばせるときは必ずおもちゃを使うのが鉄則です。
本能である以上、ねこに狩りをするのをやめさせることはできません。
本能を押さえつけられるのは大きなストレスになりますから、遊びをとおしてほどよく発散させてあげましょう。
1-6.爪とぎはやめさせられない
ねこにとって狩りのための武器である爪をとぐことは狩猟本能に根ざした行動ですから、やはりやめさせることは不可能です。
無理にやめさせようとするとストレスになり、ほかの問題行動につながるかもしれないからです。
爪とぎには、爪を鋭く保つ以外にも、気を紛らわす(ストレス発散)、自分のにおいをつけて縄張りを主張するといった意味もあります。
もし、爪とぎをしてほしくない場所がある場合は、あらかじめ保護用のシートを貼る、ねこが嫌がるにおいのするスプレーを使うなどの対策をしておきます。
もちろん、ねこが爪をといでもいい場所をきちんと用意してあげることも忘れずに。
ねこが好きなときに、好きな場所で思う存分爪をとげるように、複数の爪とぎを用意しておくとよいでしょう。
2.ねこを迎えるための環境づくり

ねこと快適に暮らすためには、習性と行動パターンを知り、そのうえで適切な室内環境を提供することが重要です。
また、ねこにとって安全な室内環境を目指すことでお互いに安心して暮らすことができます。
2-1.面積よりも高さが重要
ねこと暮らすには、ある程度の広さは必要ですが、面積よりも高低差、つまり、上下運動ができる場所があるかどうかのほうが重要だと言われています。
上にも書いたように、ねこは高い場所に登るのが好きな動物です。できれば、人間の目線よりも高い場所があるとよいでしょう。
キャットタワーを用意するのが簡単ですが、置き場所がない場合は家具の配置を工夫して上まで登れるようにするといった方法もおすすめです。
2-2.ねこと暮らすために必要な面積は?
ねこを飼うのに必要な部屋の面積は、ねこ1頭+人間1人に対して20㎡(平方メートル)とされています。
おおざっぱには6畳間×2程度です。
多頭飼いの場合は、ねこ1頭増えるごとにプラス10㎡の広さが目安となります。
また、来客などの際にねこが隠れられる場所、ひとりになって休める場所も必要です。
ねこのプライバシーを確保する意味でも、ねこ1頭につき、それぞれ専用に使える部屋を用意するのが理想と言えます。
2-3.模様替えはストレスのもと
ねこはとても繊細で、環境の変化にも敏感です。そのため、部屋の模様替えが大きなストレスになってしまいかねません。
ねこを迎え入れたあとは、大掛かりな模様替えは避け、家具などの移動も最小限にとどめるのが原則です。
故障した家電の入れ替えなどでやむを得ない場合は、新しい家具や家電をねこのにおいがついた毛布やタオルでこするなどするとよいかもしれません。
ねこは自分のにおいがついたものには不安を感じにくいと考えられるからです。
2-4.ものは片付ける・飾らない
ねこは高い場所にも軽々と登ります。そして、気になるものには触らずにはいられません。
ですから、ねこと暮らすなら、大事なものは蓋つきの箱や引き出しなどにしまう、落とされて困るものは高い場所に飾らないというのが基本中の基本となります。
また、誤飲誤食の危険性があるものはねこの手の届かない場所に片付けておきましょう。
とくに、紐状のものは危険ですので、絶対に出しっぱなしにしないように注意してください。
2-5.室内にはねこにとって危険なものがいっぱい
私たち人間にとってはなんでもないものでも、ねこにとっては危険なものは驚くほどたくさんあります。
その中でも注意してほしいのが植物です。ねこは肉を食べるのに適した体に進化したこともあって、植物の毒性に対する耐性はあまりありません。
とくに危険なのがユリ科の植物で、花や葉、茎はもちろん、花粉やユリを生けている花瓶の水を少し摂取しただけでも死に至る可能性があるとされています。
また、ネギやタマネギ、ニラなども中毒を起こす危険性が高い植物として知られています。
ねこにとって危険だと言われている植物は実に700種類以上もあるため、なにを避ければいいのかを正しく把握するのは困難でしょう。ですから、室内には植物を持ち込まないのがいちばんの対策となります。
野菜なども放置せずになるべく早く冷蔵庫などに片付けましょう。
ほかにも、アロマやにおいの強い柔軟剤、香水などもねこにとっては危険性が高いものとしてあげられているので注意してください。
2-6.自宅の脱走防止対策を徹底する
ねこは脱走の名人。体格にもよりますが、一般的なサイズのねこは10cmの隙間を通り抜けることができるといわれています。
ねこの脱走ルートは多い順に以下のようになります。
- 1.玄関
- 2.窓
- 3.ベランダ
- 4.キャリーバッグ
玄関からの脱走は家族の出入りのほかに、宅配便の対応をしている隙に外に出てしまったというケースが多いです。
窓からの場合は網戸を破ったり、自分で開けたりして外に出るので油断はできません。
玄関には柵を設置する、網戸は猫用のものに張り替える、窓に柵をつける、網戸ストッパーをつけるといった対策をすることで脱走を防げます。
また、ベランダからの脱走対策では、外に出さないというのが確実です。
通院などでキャリーバッグに入れる際は、ねこを洗濯ネットに入れるほか、キャリーバッグをネットに入れる方法もあります。
3.猫の飼育費用

ねこの生涯に必要な飼育費用は、平均寿命の15歳まで生きるとして、109万〜255万円となります。
内訳は以下のとおりです。
- ・初期費用:4万〜10万円(キャリーや食器、ケージなど)
- ・月あたり:5,500円〜1万3,000円(食費、消耗品費、医療費など)
月あたりの費用は、与えるキャットフードや使う猫砂などによって大きく異なります。
また、出張や旅行などでペットホテルやペットシッターを利用する機会が多いなど、ライフスタイルによっても変わってくるでしょう。
そのほか、病気や怪我といった思いがけない出費もありますし、家具や家電を壊される可能性も考えて、いざというときのための貯金もしておきたいところです。
※ねこにかかる費用については、ねこかぞくブログ「ねこはお金がかからない?ねこの一生に必要なお金」でも解説しています。
まとめ
ねこの飼育書を読んだだけでは見えてこないねこの行動、習性、部屋作りについて焦点をあてて紹介しました。
ねこと信頼関係を築き、互いに快適に暮らしていくためには、ねこの習性を知り、行動パターンを把握したうえで、室内の環境を整えるなどの工夫が必要となります。
一見難しく感じることもあるかもしれませんが、ねこと暮らしている人たちは普通にやっていること(キャットタワーを設置するなど)も多いのでご安心ください。
最後になりましたが、ねこの習性を知ることは、愛猫が快適な暮らしを送るために欠かせない一方、ねこの問題行動を減らし、飼い主さんが快適に暮らせるようにするためでもあることを知っていただければと思います。
「ねこを飼いたいな」と思ったら、ねこの習性についても勉強することをおすすめします。