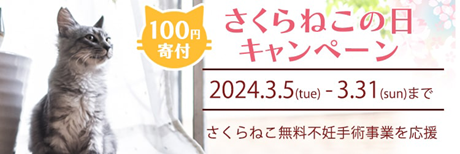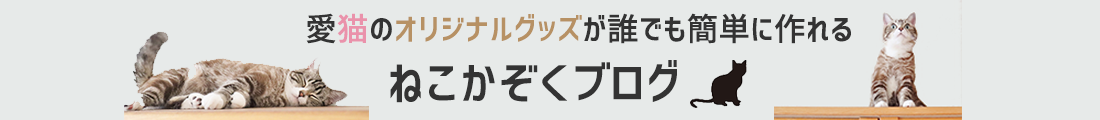
もしもの時のためにねこの輸血を学ぼう!

ねこがケガをした時や病気になった時など、輸血が必要になることがあります。しかし、人間とは違い、いざ輸血が必要、という時に血液型が分からなかったり、輸血用の血液がなかったりといったことも起こりえます。いざという時のために、輸血が必要になるケースや輸血のルール、輸血用の血液を確保する方法について知っておきましょう。
もくじ
1.ねこの血液型を知ろう
∟1-1.ねこの血液型は3種類
∟1-2.血液型を調べる方法
2.ねこの輸血を知ろう
∟2-1.輸血が必要なケース
∟2-2.違う血液型で輸血はできる?
∟2-3.ねこの輸血は難しい
3.輸血用血液を確保する方法
∟3-1.他のねこに分けてもらう
∟3-2.自分の血液を輸血する
∟3-3.人工血液が実用化される可能性も!
まとめ
1.ねこの血液型を知ろう

まずは輸血について知るために、ねこの血液型の種類や調べる方法について解説します。
1-1.ねこの血液型は3種類
ねこの血液型は3種類。A型、B型、AB型です。人間の血液型とは異なり、O型は存在しません。また、遺伝の仕方も人間とは異なります。親猫の血液型と、生まれる可能性のある子猫の血液型を表にすると、以下のようになります。
| 親猫の血液型 | A型 | B型 | AB型 |
| A型 | A型 | A型 | A型※ |
| B型 | A型 | B型 | AB型 |
| AB型 | A型※ | AB型 | AB型 |
※A型とAB型のねこからAB型のねこが生まれるケースもあります。
血液型の分布は猫種によって異なりますがA型が圧倒的に多く、日本では70~80%がA型です。B型が10%未満、AB型はほとんど出現しません。
1-2.血液型を調べる方法
ねこの血液型は動物病院で調べられます。
採血(数滴程度)を行い、判定キットを利用することで血液型が分かります。キットがない場合は血液を検査センターに送り、血液型を調べます。
また、輸血する側とされる側の血液を混ぜ合わせ、凝固しないかを確認する交差適合試験(クロスマッチ)で輸血できるかどうかを調べることも可能です。
2.ねこの輸血を知ろう

ねこの血液型についての基礎知識を押さえたところで、続いてねこの輸血について解説します。もしもの時のために、輸血が必要になるケースや輸血のルールについて知っておきましょう。
2-1.輸血が必要なケース
輸血が必要になるケースとしては、大きく分けて以下の2つがあります。
・ケガや手術
ケガや手術により体に傷が入り大量に出血した場合、輸血により血液を補う必要があります。
・病気
病気により貧血や内臓からの出血を起こしている場合、それを補うために輸血をする場合があります。例えば腫瘍や腎臓病、骨髄性白血病などが挙げられます。
2-2.違う血液型で輸血はできる?
人間と同じく、ねこも異なる血液型同士での輸血は原則としてできません。異なる血液型の血液が混ざると、血液内の抗体がお互いの赤血球を異物と見なし、機能不全に陥る恐れがあるためです。
特にB型のねこにA型の血液を輸血するのは大変危険です。B型のねこは、A型の血液に対し、激しい拒絶反応を示します。発熱や嘔吐、嗜眠といった症状を引き起こし、最悪の場合死亡することもあります。
2-3.ねこの輸血は難しい
ケガや病気で輸血が必要になっても、輸血用の血液がないケースも少なくありません。人間の場合は血液センターに血液が保存されており、必要に応じて輸血を受けることができます。しかし、ねこには血液センターはありません。また、ねこの血液は長期保存が難しいため、動物病院で輸血用血液をストックすることも困難です。
それでは、ねこの輸血用血液はどのように確保すれば良いのでしょうか。次の項でご紹介しましょう。
3.輸血用血液を確保する方法

先ほど触れた通り、ねこの血液は長期保存に向いていません。それでは、輸血をする際、輸血用血液はどのように入手すれば良いのでしょうか。ねこの輸血用血液を確保する方法をいくつかご紹介します。
3-1.他のねこに分けてもらう
多くのケースでは、他のねこから直接血をもらって輸血をします。他のねこに血を分けてもらう方法としては、以下のようなものがあります。
【1】知り合いのねこ
友人や知人のねこに献血を依頼する方法です。普段からお互いのねこの血液型について情報を交換し、もしもの際にはお互いに献血をする約束をしておくと安心です。
【2】同居ねこ
多頭飼いしている場合は、同居ねこの血液を輸血することもできます。友人や知人のねこに頼むよりスムーズに輸血できる点がメリットです。もちろん、血液型が一致していなければ輸血は難しいので、前もって検査をしておきましょう。
【3】供血ねこ
大規模な病院では、輸血用の血液を提供するねこを生活させているところもあります。このようなねこを「供血ねこ」といいます。
また、病院によっては飼い主にドナー登録を呼びかけているところもあります。ドナー登録したねこは、必要に応じて血液を提供します。そのお礼として、病院に写真を掲載したり、健康診断が無料になったりといった特典がある病院もあります。
供血ねこの条件は病院により異なりますが、その中の一例をご紹介しましょう。
- ・1~7歳の健康なねこである
- ・体重は4キロ以上
- ・ワクチン接種を毎年受けている
- ・完全室内飼いで、屋外のねことの接触がない
- ・メスの場合は避妊手術を受けており、妊娠したことがない
- ・輸血の経験がない
- ・落ち着いて採血できる
自分のねこを供血ねこにしたい場合は、まずは動物病院に詳しく話を聞き、条件や採血の方法、リスクについて納得したうえでドナー登録しましょう。
3-2.自分の血液を輸血する
自分の血液を輸血する「自己血輸血」という輸血法もあります。自分の血液を輸血、と聞いてまず思い浮かべるのが、手術前に血液を抜いてストックしておく「貯血式自己血輸血」でしょう。
他には、手術前に血液を抜き、その分を輸液でまかないながら手術を行い、血液を戻していく「希釈式自己血輸血」や、手術時に出た血液を集めて血管内に戻す「回収式自己血輸血」といった手法もあります。
他のねこの血液を輸血した場合、血液由来の感染症や、免疫低下によってがんの発生率が上がるといったリスクがありますが、自己血輸血であればその心配はありません。その反面、自己血輸血には専門的な器具が必要で、準備に手間がかかるというデメリットがあります。
3-3.人工血液が実用化される可能性も!
今はまだ実用化にはいたっていませんが、ねこの人工血液の研究も進められています。2018年3月、中央大学と宇宙航空研究開発機構(JAXA)の共同研究チームにより、ねこの人工血液の開発に成功したという報告がありました。
血液に含まれる赤血球は、酸素を運ぶという非常に重要な役割を持っています。中央大学の小松教授は赤血球の代わりとなる人工酸素運搬体「ヘモアクト」の合成に成功、その成果を元に、JAXAと協力してねこ用ヘモアクトの開発に着手しました。
国際宇宙ステーション「きぼう」の研究室内で、無重力という空間を生かした研究が進められ、ついにねこ用ヘモアクトが完成しました。
ねこ用ヘモアクトは粉末状態で保管ができ、合成が容易。血液型がないため拒絶反応を起こすこともありません。
このヘモアクト(人工血液)が実用化されたら、ねこの輸血不足問題は一気に解決するかもしれません。そして次のステップとして、人の人工血液の開発も進められるかもしれません。宇宙で作られたねこの人工血液が、ねこだけではなく人の命も救う…希望に満ちた明るいニュースですね。
まとめ
動物医療が進歩したことにより、ねこの寿命も大きく伸びています。しかし、その分輸血の必要性も増しており、ねこの輸血用血液不足は深刻化の一途を辿っています。
もしもの時のために輸血を受けられるようにするには、まず愛猫の血液型を確認しておくことが重要です。また、行きつけの動物病院では輸血用血液の確保ができているかを確認したり、友人・知人ともしもの際にお互い助け合うことを約束したりするなど、普段から輸血について考えておく必要があります。
いつかはねこ用の人工血液が実用化され、輸血用血液不足問題は解消されるかもしれません。その時までは、飼い主が輸血の知識を知り、愛猫の命を守るための準備をしておきましょう。
- ねこがケガした、誤飲した!いざという時の応急処置を学ぼう
- 「ねこの血圧」徹底解説!測り方や血圧の数値から分かる病気を知ろう
- ねこのギネス記録!世界一の長寿や子だくさん、芸達者なねこはだれ?
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP1-10!定番からレア猫種までご紹介!
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP11-20定番からレア猫種までご紹介!
- ライフステージごとのねこの魅力!子ねこもシニアねこもみんなかわいい!
- FIP(猫伝染性腹膜炎)から愛猫を守ろう!予防法や治療法を解説
- ねこの毛の色が変わることってある?その理由とは
- 「内部寄生虫」あなたの愛猫は大丈夫?主な種類と症状、治療法を解説
- 雨の日、晴れの日、ねこはどうなる?天気ごとのねこのケアを解説!