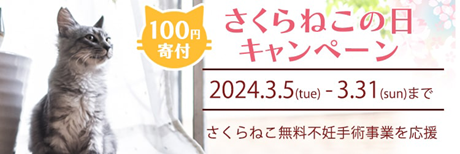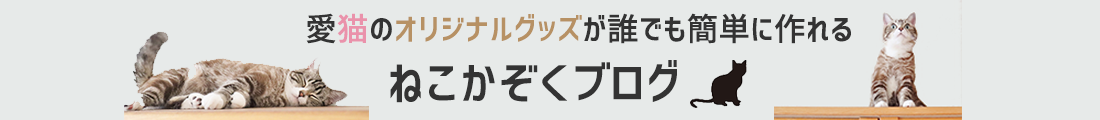
ねこ殺処分の実状と自治体や団体の取り組み-今後の課題と対策も紹介

かわいらしくて愛嬌のあるねこを衝動的に飼いたいと思うってしまうことはありますよね。
しかし、むやみにねこを飼ってしまうのは良くありません。
一時的な感情に負けて飼ったはいいもの、育てきれずに飼育放棄してしまい、結果として殺処分されてしまうねこを増やしてしまうからです。
今回は、ねこの殺処分をめぐる環境についてご紹介していきます。
目次
1.ねこの殺処分の実状
1-1.殺処分件数と推移
1-2.なぜ殺処分されてしまうのか
1-3.殺処分の方法
1-4.殺処分されてしまうねこが、減少しても安心できない理由とは
2.自治体の取り組み
2-1.横浜市
2-2.千代田区
2-3.奈良市
2-4.名古屋市
3.引き取りや殺処分を減らすための課題と対策
3-1.野良ねこへの不要なえさやりを止める
3-2.動物愛護センターへの誤った認識を改める
3-3.不妊治療をする
まとめ
1.ねこの殺処分の実状

ねこは年間でどのくらい殺処分されてしまっているかご存じでしょうか。
またなぜねこの殺処分は行われてしまうのでしょうか。
1-1.殺処分件数と推移
2020年度に引き取られたねこは4万4,798匹もいます。
2017年度は6万2,137匹、さらにさかのぼり2014年度には23万7,246匹が引き取られていました。
これは保健所や自治体の呼びかけもあり、年々着実に引き取り件数は減っています。
特に国と自治体が推し進めてきた、ねこの殺処分ゼロ活動による効果が大きいです。
ただ、2020年度に殺処分されたねこは1万9,705匹なので、引き取られたねこの約半数は殺処分されてしまったことになります。
そして殺処分されてしまうねこのほとんどが生後間もない子ねこであるのが実状です。
1-2.なぜ殺処分されてしまうのか
ねこは年に複数回出産することができ、1度に5匹前後産むことができます。
さらに生後半年ほどで妊娠できるようになるので、一生のうちに産めるねこの数が多いのが特徴です。
愛猫が生んだねこも育てきれれば良いのですが、育てきれずに、外に放してしまう飼い主が多いのです。
子ねこが増えると目が行き届かないねこが多くなるとともに、鳴き声やふん尿のトラブルも増えます。
このような問題が起きないためにも避妊手術や去勢手術をするべきであるのです。
しかし、去勢史実や避妊施術を施していないねこの飼い主が多く、結果として手術をしていないことが、ねこの殺処分に繋がっています。
また東日本大震災のような天災により、飼い主とねこが離れ離れになり、保護され最終的に殺処分されてしまうというケースもあります。
1-3.殺処分の方法
ねこの殺処分は二酸化炭酸ガスによる窒息死か、薬剤を注射することによる安楽死によって行われます。
二酸化炭酸ガスを用いた殺処分はドリームボックスという箱にガスを入れます。
二酸化炭酸ガスを入れることによって、二酸化炭素の濃度を上げ窒息させますが、ガスを入れ終わった後も確実に殺処分するため、扉は15分閉じたままとなります
このドリームボックスという名前は、眠るように安らかに旅立てるようにという願いを込めて命名されたようです。
ねこは保健所や動物愛護団体によって持ち込まれると、3日~7日経っても飼い主が見つからない場合、殺処分されてしまいます。
育てきれなくなった飼い主がとりあえずはと、保健所や動物愛護センターにねこを連れ込むことが、不要なねこの殺処分を助長させてしまっています。
1-4.殺処分されてしまう猫が減少しても安心できない理由とは
年々ねこの殺処分が減っているのは、動物愛護団体による引き取りは増えています。
これは保健所による引き取り件数が減った結果、民間団体で引き取るねこが増えたということです。
結局、引き取られているねこの総数が減っているとは言えませんし、正確な数を把握することもできません。
この保健所の引き取りが減った理由は、それまでの、ねこが可愛くないから育てられない引き取っても欲しい、引っ越すことになり飼えなくなったなどの理由で保健所がねこを引き取れなくなったからです。
逆に言えば、2012年の動物愛護法改正までは、これらの理由で保健所はねこを引き取ってくれていたということです。
現状、民間団体は保健所に相手にしてもらえなかったねこの最期の行き場になっています。
ただ、その民間団体にもねこを収容できるキャパの限界はあります。
2.自治体の取り組み

まだまだ多くのねこが殺処分されてしまっていますが、年々その数が減少しているのは、各自治体の努力があります。
ねこの殺処分を減らすためにさまざまな工夫を行っている自治体を紹介していきます。
2-1.横浜市
神奈川県横浜市は、ねこの殺処分根絶に力を入れている自治体です。
1968年から不妊手術の助成をしています。市内には、ねこが快適に過ごすことができ、またねこを飼育するための教育を行っている動物愛護団体があります。
ガラス越しに中の様子が見られるようになっており、施設内でのねこの様子が、外からでも分かるようになっています。
譲渡の際には、引き取る飼い主に対しても、ねこを飼う上での教育を行うのです。
このような民会団体や市の活動が成果となり表れ、2010年度の殺処分数は2007年度の半分以下まで抑えることができました。
2-2.千代田区
東京都千代田区では、野良ねこや飼い主がいないねこの不妊手術費用を助成する制度があります。
現在では東京23区内に不妊手術助成制度がある区は21か所ありますが、その先駆けとなったのが千代田区です。
2001年に千代田区のボランティア団体「ちよだニャンとなる会」が発足しました。
この団体は飼い主がいないねこのご飯や排泄のお世話、また手術を受けさせるため、動物病院へ連れていき、終了後はもとの住処に戻すという活動を行っています。
千代田区とちよだニャンとなる会が中心となり、会の発足から12年間で2000匹のねこに手術を施しました。
その結果、ねこの殺処分と苦情が激減するという効果が出ました。
2-3.奈良市
奈良市では複数の取り組みをすることで、2018年の犬ねこの殺処分が1件にまで減少させました。
環境省がすすめる「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」の項目をもとにして、奈良市でも独自にプロジェクトを立ち上げ活動を始めました。
例えばボランティア団体が、保護したねこを全面的にお世話をして、その後、ねこを飼いたいという方に譲渡する運動です。
団体とねこが欲しいという人の集まりの場は、当初は年に6度設けられました。
引き渡しをする際に、終生飼育への誓約をしてもらったり、お店に対してはマイクロチップ装着させてから、譲渡したねこを販売するよう促すようにしたのです。
結果、目に見える殺処分減少の効果が出ることとなりました。
2-4.名古屋市
愛知県名古屋市では、ねこの殺処分ゼロに向けて、犬猫サポート寄附金を作りました。
この寄附金は、ふるさと納税を通じてサポートできる仕組みになっています。
動物愛護センターで保護された犬とねこの、次の引き取り手が現れるまでのご飯や薬、ミルク代に充てられます。
結果的に、ねこがすぐに殺処分されることがなくなり、引き取りから殺処分までの期間が延び、殺処分されてしまうという犬ねこが減少しました。
3.引き取りや殺処分を減らすための課題と対策

保健所に引き取られてしまうようなことや殺処分などを減らし、ねこの不幸な待遇をどうすれば、より改善していく必要があります。
私たちにはどのようなことができ、何をしてはいけないのでしょうか。
3-1.野良ねこへの不要なえさやりを止める
引き取られるねこのおよそ8割が野良ねこで、さらにその8割のねこに子ねこがいます。
野良ねこがどんどん増えてしまう理由の1つにえさやりをする人の存在があります。
かわいらしいねこを見ると、懐いてもらいたくて、ご飯をあげたくなる気持ちは分かります。
ただし、ご飯はあげるけど、排泄のお世話やしつけはしませんというのはあまりに無責任です。
1人でもえさやりを定期的にする人がいると、ねこは他のねこを引き連れてやってきてしまいます。
このようなえさやりをする人への指導と、えさやりをする人を根絶することが、ねこの殺処分を減らすための近道です。
3-2.動物愛護センターへの誤った認識を改める
飼い主の中には、動物愛護団体を困ったときにねこを引き取ってくれる、なんでも屋さんだと思っている人が多いのも実情です。
民間団体や、地方自治体では、ねこを引き取ったあと一定の期間が経ってしまうと殺処分されてしまいます。
ねこを育てるのが面倒になったから、あとはお願いしますという無責任な飼い主の気持ちが、ねこの殺処分につながってしまいます。
多くの人に動物愛護団体が、単なるねこに関する受け皿組織ではないことを知ってもらう必要があります。
3-3.不妊治療をする
不妊去勢手術を行えば、子ねこが生まれることがありません。
つまり、飼い主が面倒を見切れなくなり、無責任に野放しにしたり、動物愛護団体や保健所に駆け込むということがなくなります。
不妊治療をねこに受けさせていない飼い主のおよそ40%が手術する必要がない、そして30%が手術費が高いからとその理由について回答しています。
1匹目のねこを飼う時に、不妊手術または去勢手術を行うことを想定してから、飼い始めれば、手術費が高いという理由で、手術が受けられないという事態は免れます。
また、手術をする必要がないと考えている飼い主には、もしも飼いねこに想定外の子ねこが生まれた場合、動物病院や保健所の前にねこを置き去りにして飼育放棄をしたことが発覚した際には犯罪になるという認識を持たせる必要があります。
その場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
飼い主には、このような知識を勉強してもらう機会を設けて、不妊治療を飼いねこに受けさせるようしなければ、ねこの殺処分は減りません。
まとめ
ねこの殺処分件数は、自治体や民間団体の活動の成果もあり、年々減少傾向にあります。
ただし、それでも一部の責任感のない飼い主や、定期的に野良ねこにご飯を与える人たちもおり、殺処分されてしまうねこを生み出す原因となっています。
ねこの殺処分ゼロに向けて、より一層の啓蒙活動の実施に励む必要があります。