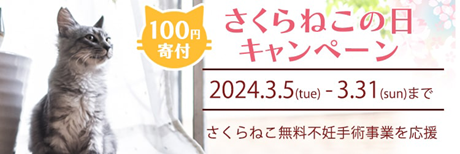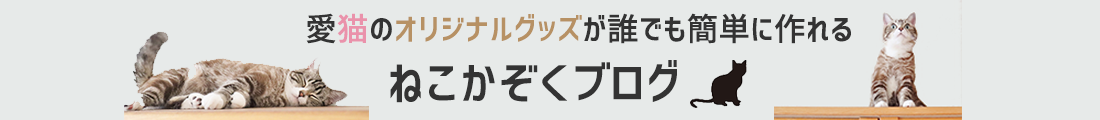
犬猫のマイクロチップ義務化!痛くない?費用は?徹底解説!

2022年6月1日より、改正動物愛護法が2022年に施行されることになります。
それによって、ペット販売業者に対し、ねこや犬に対しマイクロチップを装着することが義務となるのです。
このマイクロチップ装着は、迷子や遺棄による不幸な、ねこや犬を減らすために有効であると考えられています。
しかし、大切なねこの体に異物を入れることに抵抗を感じている、費用や登録方法が分からず不安、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の記事では、マイクロチップのメリットや、ねこの体への影響、装着の手順についてご紹介します。
目次
1.マイクロチップとは
2.マイクロチップ義務化とは?飼い主がすべきことはある?
3.ねこの命を守るマイクロチップ
∟3-1.迷子になった時に再会しやすい
∟3-2.捨てねこ、捨て犬を減らす
4.マイクロチップ装着の手順と料金
∟4-1.動物病院に相談する
∟4-2.マイクロチップの装着を行う
∟4-3.登録の手続きをする
∟4-4.マイクロチップ装着にかかる料金
5.マイクロチップQ&A
∟5-1.装着は痛くない?
∟5-2.異物を体に入れて大丈夫?
∟5-3.すでに民間登録団体に登録している場合はどうすればいい?
∟5-4.装着後に変わったことがあったらどうする?
まとめ
1.マイクロチップとは
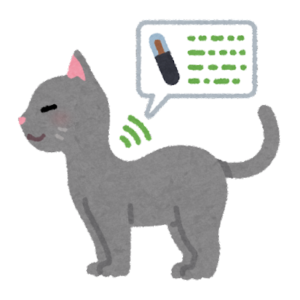
マイクロチップは電子標識器具の一種です。
円筒形をしており、直径は2ミリ、長さは12ミリ程度で、お米の粒を縦に2つ並べたくらいのサイズです。
マイクロチップには15桁の個体識別番号が記録されており、専用のリーダーで読み取ることができます。
これを動物の体に埋め込むことで、その動物に関する情報が得られる個体識別証になります。
迷子札や首輪と違い、汚れたりなくなったりして判別不能になることはありません。
また、電源を必要としないため電池がなくても作動し、30年程度使用することができます。
ねこの寿命を考えると、「半永久的に使える名札」であるといえるでしょう。
2.マイクロチップ義務化とは?飼い主がすべきことはある?
法改正により、2022年6月1日より、ペットの販売を行う事業者は、取り扱う犬やねこにマイクロチップを装着することが義務付けられました。
そのため、法改正以降にねこを購入した場合には、マイクロチップに登録されている情報の更新申請が必要になります。
なお、すでにねこを飼っている、知人や譲渡会から譲り受けたという場合は、飼い主に装着義務はありませんが、推奨はされています(努力義務)。
3.ねこの命を守るマイクロチップ

マイクロチップ義務化は、ねこや犬の命を守る手段になりうると期待されています。
具体的な効果として考えられるのは以下の2点です。
3-1.迷子になった時に再会しやすい
マイクロチップ義務化のきっかけとなったのは、1995年の阪神・淡路大震災後です。
多くのねこや犬が迷子になったことから、導入を求める声が上がるようになりました。
マイクロチップには飼い主の情報が登録されているため、万が一ペットが迷子になってしまった場合も飼い主の元に帰ってくる可能性を高められます。
ただし、マイクロチップにはGPSのように居場所を知らせる機能はありません。
また、ねこを保護した人にマイクロチップに関する知識がない場合は読み取りをしてもらえないため、返還が難しくなることもあります。
マイクロチップは万能ではないことを心にとめ、普段から迷子防止や災害発生時の対応について考えておかなければなりません。
3-2.捨てねこ、捨て犬を減らす
ペットブームによりねこや犬を飼う人が増えた結果、世話をしきれずねこや犬を捨ててしまうという事態も多く起こるようになりました。
また、悪質なペットショップやブリーダーが、買い手がつかなかったり、健康状態が悪かったりするねこや犬を遺棄する事件も相次ぎ、社会問題となっています。
マイクロチップを義務付け、飼い主や所有者を明確にすることで、遺棄を防止する効果があると期待されています。
4.マイクロチップ装着の手順と費用

先ほどご紹介した通り、マイクロチップはねこを守るための重要な手段になりえます。
今回の法改正をきっかけとして、愛猫にマイクロチップを装着したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自分でマイクロチップ装着を行う方のために、その手順と費用についてご紹介します。
4-1.動物病院に相談する
マイクロチップの装着は必ず動物病院で行います。
ねこの場合は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
ねこの体格や健康状態によっても異なりますので、獣医師と相談しながら日にちを決めましょう。
4-2.マイクロチップの装着を行う
マイクロチップは注射針より少し太い、専用の注射器のようなものを使ってねこの首の後ろ当たりの皮下に注入します。
4-3.登録の手続きをする
マイクロチップ装着後、動物病院からもらった登録申込書に必要事項を記入し、登録料を支払います。
登録は書面とオンラインから選ぶことができます。
登録証明書が届いたら、大切に保管しておきましょう。
4-4.マイクロチップ装着にかかる料金
マイクロチップ装着にかかる料金は以下の通りです。
【1】装着費用
装着費用は動物病院によって異なりますが、ねこの場合は数千円~1万円程度であると考えておくと良いでしょう。
【2】登録手数料
登録手数料は以下の通りです。
・紙での申請 1,000円
・オンライン申請 300円
5.マイクロチップQ&A

マイクロチップにはメリットも多いですが、ねこの体への影響や登録変更など、不安点・疑問点も多くあります。
Q&A方式で回答していきますので、参考になさってください。
5-1.装着は痛くない?
先ほどご紹介した通り、マイクロチップは米粒くらいのサイズで、注射器を使って注入します。
痛みはほとんどないとされ、基本的には無麻酔で行われます。
避妊手術や口腔ケアなど、麻酔を使った施術の際に一緒にできることもありますので、心配な場合は獣医師に相談しましょう。
5-2.異物を体に入れて大丈夫?
マイクロチップが義務化されたとはいえ、大切なねこの体に異物を入れることに不安を覚える方も多いのではないでしょうか。
しかし、現在のところマイクロチップの装着による動物への健康被害はほとんどありません。
日本においては、副作用やショック症状などの事例は1件も報告されていません※。
まれに体内での移動が見られますが、読み取りに支障が出る範囲ではありません。
レントゲン撮影やCTスキャンも問題ありませんが、MRIの画像は乱れる場合があります。
処置を受ける際には、獣医師にマイクロチップが装着されていることを伝えるようにしましょう。
※公益社団法人 日本獣医師会 「動物の福祉及び愛護」(2022年3月時点)
5-3.すでに民間登録団体に登録している場合はどうすればいい?
ねこのマイクロチップ登録をすでに民間の登録団体(AIPO、JKC、Fam)などで済ませている場合は、環境省のデータベースにも登録することが可能です。
以下のサイトから2022年6月1日より登録可能で、登録料は無料です。
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト
5-4.装着後に変わったことがあったらどうする?
マイクロチップを装着した後、ねこや飼い主に何らかの変化があった時は、登録情報の変更申請が必要になる場合があります。
具体例をご紹介しましょう。
【1】飼い主の情報が変わった場合
飼い主の引っ越しや結婚などにより、住所、氏名、電話番号などが変更になった場合は、登録内容変更の届出が必要になります。
届け出はオンラインと紙、どちらでも可能で、手数料はかかりません。
【2】他の人にねこを譲る場合
他の人にねこを譲る場合は、飼い主情報の変更が必要になります。
譲り先の人に登録証明書を渡し、申請をしてもらってください。
なお、登録証明書は電子データ(pdf)で渡しても構いません。
【3】ねこが亡くなった場合
ねこが亡くなった場合は、指定登録機関に死亡の届出をする必要があります。
こちらも届け出はオンラインと紙、どちらでも可能で、手数料はかかりません。
まとめ
ねこ・犬のマイクロチップ義務化と、装着の手順や費用、注意点についてご紹介しました。
義務化以前からねこを飼っている、もしくは購入ではなく譲渡でねこをお迎えしたという場合は、マイクロチップ装着は必ずしもしなくてはならないというわけではありません。
しかし、マイクロチップを装着することで、大切なねこが迷子になった時、自分の元に帰ってくる可能性が高まるという効果が期待できます。
今回の法改正をきっかけとして、マイクロチップ装着を始め、万が一の時に大切なねこの命を守る方法について考えてみてはいかがでしょうか。