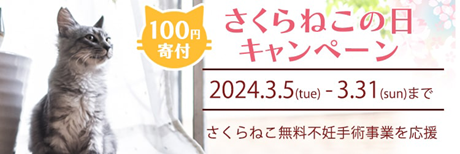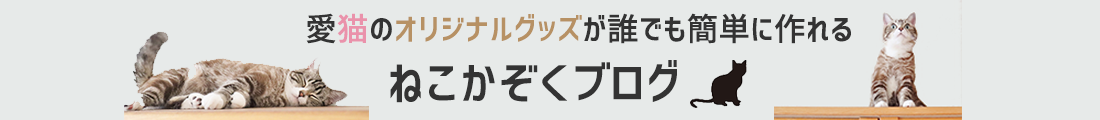
ねこの喧嘩は止めた方がいいの?原因と対処法を詳しく解説します

去勢をしていないオス猫同士の場合は喧嘩になりやすいと言われています。
愛猫が喧嘩をはじめると「怪我をしないかな」と不安になったり、「止めた方がいいかな」と悩んだりする飼い主さんも多いのではないでしょうか。
今回は、そんな飼い主さんの疑問を解消するために、ねこの喧嘩の原因と対処法を詳しく解説していきます。
目次
1.ねこはどうして喧嘩をするの?
∟1-1.縄張りを守るための喧嘩
∟1-2.発情期のメスねこを取り合って喧嘩
∟1-3.飼い猫の喧嘩
2.ねこの喧嘩にはルールがある
3.喧嘩と遊びの見分け方
4.ねこの喧嘩の対処法
∟4-1.ねこの喧嘩は止めない
∟4-2.お互いに相手の姿を見えないようにする
∟4-3.おやつやおもちゃなどで気をそらす
5.ねこに喧嘩をさせないための方法と注意点
∟5-1.相性が悪いねこは部屋をわける
∟5-2.パーソナルスペースの確保
∟5-3.喧嘩の仲裁は怪我に注意する
∟5-4.怪我防止のために爪を切っておく
まとめ
1.ねこはどうして喧嘩をするの?

ねこは基本的に喧嘩を避ける動物です。
万が一怪我をしてしまうと外で暮らすねこにとっては命取りにもなりかねないからです。
ですから、どんなに気に入らない相手がいても、いきなり襲いかかるようなことはありません。
「ウー」と唸り声を上げたり「シャー」と威嚇したりして喧嘩を回避しようとします。
しかし、ねこも生きていくうえで戦わなければいけないときがあるのです。
では、どのようなときにねこは喧嘩をするのでしょうか。
1-1.縄張りを守るための喧嘩
ねこはとても縄張り意識の強い動物です。とくにオス猫は縄張り意識が強く、ほかのねこの侵入を許しません。
ねこの縄張りは、休む、ご飯を食べる、子育てをするホームテリトリーと狩りをするためのハンティング・エリアの2つにわかれています。
ホームテリトリーはねこにとってのプライベート空間です。
家族や同居のねこの侵入を許すことはあっても知らない人間や動物が侵入すると、激しい喧嘩になることがあります。
その周りにあるのがハンティング・エリアで、数頭のねこと共有します。
飼い猫の場合は、家の中がすべてハンティング・エリアになります。
ホームテリトリーほどの強い縄張り意識はありませんが、知らないねこが侵入してくれば喧嘩に発展することもあるのです。
1-2.発情期のメスねこを取り合って喧嘩
オス猫は年2回の発情期(2~4月と6~8月ごろ)になると、メス猫が発する特有のフェロモンや鳴き声に誘われて集まってきます。
メス猫はその中でいちばん強いオス猫と交尾をしようとするため、メス猫を取り合って喧嘩に発展するのです。
発情期のオス猫は、いつもより気性が荒くなるため喧嘩が起こりやすいと言われています。
1-3.飼い猫の喧嘩
飼い猫の場合は、食料も安心して寝られる場所も確保されています。
ですから、一見すると喧嘩をする必要がないように思われるかもしれません。しかし、喧嘩に発展することがあるのです。
その原因のひとつが、プライベート空間が守られていないストレスです。
ねこは基本的に単独行動をする動物ですから、どんなに仲の良いねこであっても、常に近くにいるのはストレスになります。
そのため、自分の縄張りにいる同居のねこと喧嘩に発展すると考えられているようです。
また、単純に同居のねこと相性が合わないため喧嘩になることもあります。
2.ねこの喧嘩にはルールがある

ねこには喧嘩をする際に守るべきいくつかのルールがあります。
- ・勝ち目のない相手とは喧嘩をしない
- ・いきなり飛びかからずに、睨み合いながら威嚇する
- ・威嚇で互角だと判断すると喧嘩に発展する
- ・逃げ出す、うずくまるは降参のサイン
- ・一度勝敗がつくと再び喧嘩をすることはほぼない
ねこの喧嘩では体が大きい方が有利なため、体格差がある場合は小さい方が目をそらすなど喧嘩を回避する行動をします。
怪我をすると命取りになることもあるため、無理はしないのです。
体格差がないねこの場合は、お互いに睨み合いながら、毛を逆立て「ウーウー」「シャーシャー」と威嚇しあいます。
それでも引かない場合は激しい喧嘩に発展します。
どちらか一方が、その場から逃げ出すか、うずくまって反撃をしなくなったら「降参」の合図です。
ねこの喧嘩ではそれ以上の攻撃をすることはありません。
ねこの喧嘩は一度決着がつくと、その後は基本的に喧嘩になることはありません。
このように、ねこの喧嘩にはルールがあり、意外と紳士的なのです。
3.喧嘩と遊びの見分け方

ねこは遊びでも取っ組み合って激しく遊ぶことがあります。
遊びなのか、喧嘩なのかいまいち判断ができないという場合もあるかもしれません。
喧嘩の場合は、
- ・毛を逆立ててる
- ・「ウーウー」「シャーシャー」と威嚇している
- ・首の辺りを激しく噛んでいる
といった様子が見られます。
逆に、お腹を見せて寝転んだり、威嚇をしていなければ、遊びと判断してもよいでしょう。
ただし、興奮して遊び方が次第に激しくなるような場合は喧嘩に発展する可能性がありますので注意してください。
なお、子猫の場合は激しく取っ組み合って遊んだり、喧嘩ごっこで噛みついたりすることで力加減を学習します。
ねこの成長にとっては、大切な経験ですから、ある程度は見守るようにしましょう。
4.ねこの喧嘩の対処法

愛猫が喧嘩をはじめたらどのように対処したらよいのでしょうか?実はできることはそれほど多くはありません。
基本的には「見守る」。大怪我をしそうなときは仲裁をするということになります。
では、具体的にはどのように対処したらよいのでしょうか?
4-1.ねこの喧嘩は止めない
同居のねこが喧嘩をしているとついつい止めたくなりますが、「ねこ同士の喧嘩は止めない」のが正解です。
ねこは喧嘩をして決着をつけることで関係性を築きます。また、前述のとおり、ねこは勝敗が決まれば再び喧嘩をすることはありません。
ねこの喧嘩を仲裁し中途半端にすると、関係性がこじれてしまいます。怪我をしないように見守るだけにしましょう。
ただし、あまりにも激しい喧嘩で大きな怪我につながりそうなときは仲裁をすることも必要です。
4-2.お互いに相手の姿を見えないようにする
ねこがにらみ合っている状態ならば、段ボールなどを間に挟んでお互いを見えないようにするのが効果的です。
1回だけでは効果がなくても、2回、3回と繰り返しているうちに次第に気持ちが落ち着いて喧嘩を止めることができます。
4-3.おやつやおもちゃなどで気をそらす
ねこの気をそらすことで喧嘩を止める方法があります。
- ・大好きなおやつを用意する
- ・おもちゃで気を惹く
- ・霧吹きで水をかける
- ・大きな音を鳴らす
これらはあくまでも一例です。
ただし、ねこはとても臆病な動物ですから、おどかす際はやりすぎないように注意をしましょう。
5.ねこに喧嘩をさせないための方法と注意点

上にも書きましたが、飼い猫の喧嘩の原因は、パーソナルスペースがないことによるストレス、ねこ同士の相性が悪いと言ったことが考えられます。
つまり、ねこそれぞれに専用の場所をつくり、相性の悪いねこの生活空間をわけることで喧嘩を避けることができるのです。
また、対策をしても喧嘩になってしまうことがあると思います。その際の注意点も併せて紹介します。
5-1.相性が悪いねこは部屋をわける
多頭飼いで相性の悪いねこがいる場合は部屋を分けて様子を見るようにしましょう。
新しくねこを迎えるときは、とくに注意深く見守りましょう。
先住のねこにとって新入りのねこは、縄張りへの侵入者です。
とくに未去勢のオス猫同士の場合は注意が必要でしょう。
先住のねこが新入りのねこを追い払おうと喧嘩になるのはよくあることです。
最初は部屋を分けて様子を見るようにしてください。
5-2.パーソナルスペースの確保
ねこはいざというときに隠れられる自分だけの場所(パーソナルスペース)が必要です。
ねこと暮らすためには、ねこ1頭につき最低でも10平米のスペースが必要だとされています。
また、部屋数はねこ1頭につき1部屋+1部屋が理想とされています。
ねこは単独で過ごすことを好む動物です。誰にも邪魔されない専用の場所がないのは大きなストレスになることもあり、喧嘩の原因にもなります。
多頭飼いをする際はねこにとって適切な広さがあるかよく考えるようにしましょう。
5-3.喧嘩の仲裁は怪我に注意する
基本的にねこの喧嘩は見守るのが正解とされていますが、あまりにも激しく、大怪我の可能性がある場合は仲裁をする必要があります。
ねこには鋭い爪と牙がありますので、仲裁をする際には素手で止めるのは絶対に避けましょう。
上にも書きましたが、段ボールなどで視界を遮る、おやつやおもちゃなどで気をすらす、霧吹きでおどかすといった方法がおすすめです。
5-4。怪我防止のために爪を切っておく
ねこが喧嘩になった際のいちばんの心配は怪我です。
ねこの爪は大変鋭く、本気でひっかかれると大怪我をします。
喧嘩のときは本気で攻撃しますので注意が必要でしょう。
また、ねこに引っかかれることで、猫ひっかき病やパスツレラ症などの人畜共通感染症の原因になることもあります。
大切なわが子たちを守るためにも、飼い主さんが怪我をしないためにも爪はこまめに切るようにしましょう。
まとめ
ねこが喧嘩をはじめたら、止めずに見守るのが正解です。
愛猫が喧嘩をしていると心配でつい仲裁をしたくなるかもしれませんが、ねこ同士が良好な関係を築くためには、ねこのルールに従うことも必要です。
大怪我をしそうなほどの激しい喧嘩でなければ、そっと見守るようにしましょう。