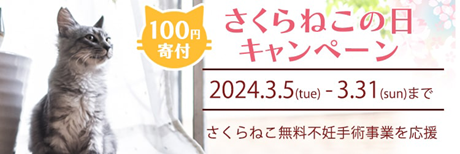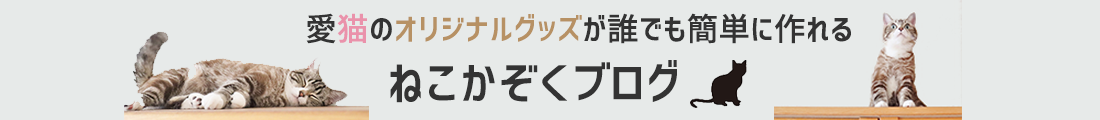
ねこの保険とはどんなもの?メリットやデメリット、選び方をご紹介

ペットにも保険があることはご存じでしょうか?
ねこを家族に迎えるなど、ペットを飼う家庭が増加している事もあり、日本でもペット保険の加入者は増加傾向にあります。
まだまだ加入率も低いのが現状です。
今回は高額になりがちなペットの医療費を軽減してくれるペット保険について解説していきます。
目次
1.ねこの保険とは
2.ねこの保険のメリット
∟2-1.経済的負担を軽減できる
∟2-2.早期発見・早期治療につながる
∟2-3.治療の選択肢が増える
3.ねこの保険のデメリット
∟3-1.掛け捨てが多い
∟3-2.全て補償されるとは限らない
∟3-3.年齢とともに保険料が上がる
4.ねこの保険の選び方
∟4-1.加入可能な年齢
∟4-2.保険料
∟4-3.補償範囲
∟4-4.補償割合
∟4-5.補償制限
まとめ
1.ねこの保険とは

ねこの保険(ペット保険)とは、ねこ向けの医療保険です。
飼い主が加入し、保険料を払うことによって、ねこがけがや病気をした際、その治療費の一部が保険会社より補填されます。
補償される対象は保険会社やプランによって異なりますが、主に以下のようなものが挙げられます。
- ・通院費 :動物病院で診察を受けた際にかかった診療費、処置費、処方薬代など
- ・入院費 :入院した際にかかる費用
- ・手術代 :ペットの手術費用や、手術の際に必要な麻酔、点滴などにかかる費用
動物病院に通った際にかかる費用のうち、以下のようなものは補償対象にならないケースがほとんどです。
- ・健康診断
- ・ワクチン接種
- ・ワクチン等の予防接種により予防できる病気
- ・傷病に当たらないもの
また、出産や去勢・避妊手術、歯石除去、爪切り、耳掃除、マイクロチップの埋め込みなども含まれません。
2.ねこの保険のメリット

ねこの保険に加入するかどうかを決める際には、メリットとデメリットを知る必要があります。
まずは、ねこの保険のメリットについてご紹介しましょう。
2-1.経済的負担を軽減できる
動物病院の診療費は自由診療であるため、全額自己負担となると飼い主に大きな負担がかかります。
現在では獣医療の進歩により、高度治療が可能になりました。
治療の選択の幅が増え、愛猫が健康に生きられるチャンスが増えるのはとても嬉しいことですが、その反面、治療費の支払いが高額、長期に渡り、負担がますます大きくなってしまうことにもつながります。
保険に加入していれば、治療代を保険によって補填できるため、経済的負担を軽減することができます。
2-2.早期発見・早期治療につながる
先ほど触れたように、ねこの治療費は高額です。
少し調子が悪そうと思っても、治療費が気になり、病院に連れて行きづらいということもあります。
しかし、ねこは体の不調をなるべく隠したがる動物です。
少し調子が悪いという時点で病院へ連れて行かないと、手遅れになってしまうことにもなりかねません。
保険に加入していれば気軽に病院へ連れて行けるため、早期発見・早期治療につながります。
2-3.治療の選択肢が増える
特に重い病気にかかった際、積極的に治療を受けるか、苦痛を押さえつつ様子を見るか、治療の方向性は飼い主にゆだねられます。
しかし、特に高度な治療や手術は高額になるため、選びたくても選べないという場合があるでしょう。
保険に加入して補償を得ることで、高額な治療や手術も行いやすくなるため、治療の選択肢を増やせます。
3.ねこの保険のデメリット

続いて、ねこの保険のデメリットをご紹介します。
ねこの保険は人間の医療保険と似ているとはいえ、少し違う点もありますので、その特徴をしっかり押さえておきましょう。
3-1.掛け捨てが多い
人間の保険には、保険料を貯蓄できる「貯蓄型保険」がありますが、ねこの保険は「掛け捨て」であることがほとんどです。
そのため健康なねこの場合、保険を利用する機会がなく、かけた保険料が無駄になってしまう場合もあります。
3-2.全て補償されるとは限らない
先ほどご紹介した通り、保険に入ったからといって動物病院でかかる費用の全てが保障されるわけではありません。
健康診断や爪切り・耳掃除、また避妊・去勢手術も補償されない場合がほとんどです。
また、先天性疾病など、プランによっては補償されていない病気もあるため注意が必要です。
それに加え、保険会社によっては「待機期間」が設けられていることもあります。
これは保険加入直後から一定期間は補償の対象外になるというものです。
たとえば、病気の待機期間が1ヶ月と定められている場合、加入直後に病気になり動物病院に行っても、治療費は補償されません。
3-3.年齢とともに保険料が上がる
ねこの保険は基本的に1年ごとに契約更新され、多くのプランではその際に保険料が上がります。
ねこも年を重ねると病気になりやすくなるため、保険料が上がってしまうというわけです。
また、更新できる年齢に制限がある保険もあります。
年を取って病気になりやすくなり、いざ保険が必要という時点になって更新ができないという事態もありえます。
4.ねこの保険の選び方
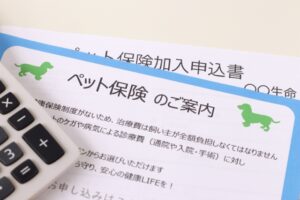
メリットとデメリットを比較し、保険に入ることを決めたけど、どうやって選べば良いか分からない……という方もいらっしゃるかもしれません。
ねこの保険に加入する際に、必ずチェックしておきたいポイントについて解説します。
4-1.加入・継続可能な年齢
先ほどご紹介した通り、加入や更新ができる年齢に制限のある保険会社・プランもあります。
診療が多くなるのはやはり高齢になってからなので、終身継続ができるというのは重要な選定ポイントになります。
また、終身継続可能な保険であっても、健康状態によっては更新ができないものもありますので、併せて確認しておきましょう。
4-2.保険料
保険に加入する際、やはり気になるのは保険料です。
しかし、目先の保険料ばかりを気にしていてはいけません。
先ほどご紹介した通り、ねこの保険料は年齢と共に上がります。
特にねこがまだ若い時に加入した場合、保険料の増加率によっては負担が大きくなり過ぎてしまう場合もあります。
その時に他の保険会社に切り替えしようとしても、ねこの年齢によっては難しいかもしれません。
直接保険会社に確認するなどして、将来的にどの程度保険料がかかるかを確認しておきましょう。
4-3.補償範囲
保険でカバーできる補償範囲についても確認しておきましょう。
保障される内容は、保険会社やプランによって異なります。
特に純血種のねこを飼っている場合、かかりやすい病気の傾向がある程度分かるため、その病気が補償対象となっているかどうかを確認しておくことが重要になります。
また、保険会社によっては「特約」が設けられているものもあります。
例えば、ねこが他の人や動物に傷を負わせたり、物を壊したりした場合に補償される、ガンで手術を受けた際に上乗せの補償がある、というようなものです。
こちらも内容をしっかり確認し、必要に応じて利用すると良いでしょう。
4-4.補償割合
多くのペット保険では、治療費の全てが補償されるわけではなく、50%、70%というように補償割合が決まっています。
補償割合によって保険料も違いますので、自分の希望に合わせて補償割合を決めるようにしましょう。
また、治療内容や治療費によっては、補償割合が決まっていても飼い主の全額自己負担となる場合もありますので、そちらも併せて確認しておきましょう。
4-5.補償制限
補償制限のチェックも重要です。
補償制限とは、補償額や通院・入院・手術の回数において設けられている補償の限度を指します。
基本的には、1年間に○円まで、○回の手術までというように定められています。
補償制限がある場合、例え保険に加入していたとしても、自己負担額が高額になってしまう場合があります。
保険を選ぶ際には、補償制限がどの程度設けられているのか、また1年ごとにリセットされるのかという点を確認しておきましょう。
補償範囲・補償割合・補償制限は手厚くなればなるほど保険料が上がります。
「保険料は高くてもいいから、安心して治療がしたい」「保険料を押さえつつ、自己負担を減らしたい」など、保険加入の目的によって選ぶことが重要です。
まとめ
ねこの保険のメリットやデメリット、選び方についてご紹介しました。
ねこの治療や通院、手術は高額になる場合もあり、飼い主の負担は決して小さくありません。
保険は必ず入らないといけないというものではありませんが、もしもの時に経済的な制限なく、愛猫に治療を受けさせてあげるための助けになります。
メリットやデメリット、補償内容を確認し、保険に加入すべきか、また加入するならどのような保険を選ぶべきか、考えてみてはいかがでしょうか。
- ねこがケガした、誤飲した!いざという時の応急処置を学ぼう
- 「ねこの血圧」徹底解説!測り方や血圧の数値から分かる病気を知ろう
- ねこのギネス記録!世界一の長寿や子だくさん、芸達者なねこはだれ?
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP1-10!定番からレア猫種までご紹介!
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP11-20定番からレア猫種までご紹介!
- ライフステージごとのねこの魅力!子ねこもシニアねこもみんなかわいい!
- FIP(猫伝染性腹膜炎)から愛猫を守ろう!予防法や治療法を解説
- ねこの毛の色が変わることってある?その理由とは
- 「内部寄生虫」あなたの愛猫は大丈夫?主な種類と症状、治療法を解説
- 雨の日、晴れの日、ねこはどうなる?天気ごとのねこのケアを解説!