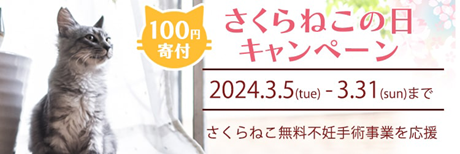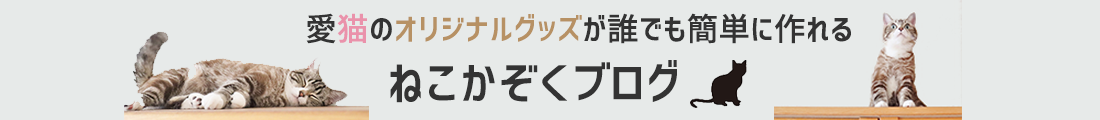
どれくらいの頻度でやればいいの?ねこの耳そうじ
ねこの健康を保つために、定期的にみてあげないといけないことに、耳そうじがあります。
日々のご飯のお世話や、爪切りなど、見てあげないといけないことが意外と多くて大変ですよ。
ねこの耳そうじについて、どうやってしてあげるのが正しくて、またどの程度の頻度でしてあげるのが、良いのでしょうか。
目次
1.頻繁にやる必要がない耳そうじ
2.ねこの耳の特徴
∟2-1.どんな形
∟2-2.体調が分かる
3.耳そうじをすべきタイミング
∟3-1.耳が汚れているときと臭いがするとき
∟3-2.耳がかゆそうなそぶりをみせたとき
4.耳そうじのやり方
∟4-1.綿棒を使う
∟4-2.ガーゼで拭く
∟4-3.洗浄液を使う
∟4-4.動物病院でしてもらう
∟4-5.アロマオイルは使わない
5.ねこが耳そうじを嫌がるときは
∟5-1.無理やりそうじをしない
∟5-2.触れ合う回数を増やす
まとめ
1.頻繁にやる必要がない耳そうじ

ねこの耳そうじは頻繁にやるべきではありません。
ねこの耳には自浄作用があると言われており、健康な状態であれば耳が汚くなることは少ないのです。
通気性がよくむれにくいからだと言われます。
特に汚れや耳あかがないのに、強くそうじしようとしたり、奥まで綺麗にしようとすると、かえって耳内を傷つける可能性もあるので、週に1度の頻度で耳そうじをする程度で大丈夫です。
ただし、飼いねことして人気の高いスコティッシュフォールドの場合は別です。
耳自体が小さく、折れているため、他の種類のねこと比べると通気性が悪く、耳あかは溜まりにやすいです。
定期的にそうじをしてあげるようにしましょう。
2.ねこの耳の特徴

ねこの耳の形や特徴を知ることで、適切な耳そうじの仕方ができます。
耳の状況を把握することで、愛猫の体調も分かりますので確認してみてください。
2-1.どんな形
ねこの耳はL字型になっています。
前方に向かって耳が開いており、音が聞こえる方向に合わせて向きが変わるため、音が聞き取りやすい仕組みになっています。
ただし、耳そうじをするという点からすると、人間とは構造が異なり、耳垢が溜まってしまうと取りにくくなっています。
2-2.体調が分かる
ねこは、耳に自浄作用があることから、汚れることが少なく耳あか出ることも少ないです。
そんなねこが耳あかを溜めてしまっているときは、体調不良のサインの可能性があります。
ねこにとって、耳は音を聞き取るだけの場所ではなく、平衡感覚を掴むための大切な器官です。
異常を感じたら、すぐに耳そうじをして、動物病院につれていってあげましょう。
3.耳そうじをすべきタイミング

基本的には週に1度の耳そうじで大丈夫です。先ほども紹介したように、耳そうじをしすぎてしまう方が、体に悪影響を及ぼしてしまいます。
そのほかには、どのようなタイミングが適切なのでしょうか。
3-1.耳が汚れているときと臭いがするとき
耳をみたときに明らかに汚れている、また臭いするときは適切な耳そうじのタイミングです。
外耳炎や耳ダニの寄生による感染症の可能性があります。
外耳炎の場合は湿度が高い時期に発症してしまうことが多く、また耳あかも多く出てきます。
気になったらすぐに、動物病院に連れていきましょう。
耳が多少黒く汚れている程度でしたら、心配はありません。
3-2.耳がかゆそうなそぶりをみせたとき
ねこが自ら耳を掻いていたら、耳そうじをしてあげるタイミングです。
ねこは、人間と違って手がないため、耳そうじを自分で上手にはできません。
耳が気になるときは、後ろ足を使って耳を掻こうとします。
ただ、うまく自分ではそうじできないため、続けてしまうと、爪で体を傷つけることになり、そこから菌が入ってしまうことも考えられます。
この様子に気づかずに放置してしまうと、外耳炎になってしまうこともありますので、よく愛猫の様子を見てあげるようにしましょう。
4.耳そうじのやり方

実際に、正しい耳そうじをするにはどうしたら良いでしょうか。
どの方法で耳そうじをするにしても、原則として優しく耳を綺麗にしてあげます。
4-1.綿棒を使う
綿棒を使うときは、人間用のものではなく、ねこ用の綿棒を使用してください。
人間用のものであると、ねこにとっては固く感じてしまうからです。
綿棒がなければ、カット綿を指先に巻き、耳を指先でほじるような感覚で耳そうじをします。
耳を傷つけないように優しくそうじをしましょう。
綿棒での耳そうじも良いですが、実際に自分の指先を使って耳そうじをする方が、力加減が調整しやすくてやりやすいかもしれません。
ただし、ねこの耳はL字になっているため、綿棒を使っても奥までは届きません。
4-2.ガーゼで拭く
ガーゼを使った耳そうじも良いです。綿棒や指を使って耳をほじってそうじをする方法ではなくは、見える範囲を優しく拭き取ってあげるというやり方です。
綿棒を使った耳そうじと同様で優しくなでるような感覚で耳そうじをしてあげましょう。
ねこは皮膚が薄いので、少しでも力が伝わってしまうと痛いと感じてしまいます。
ガーゼは、水で軽く湿らせたものを使用するのがおすすめです。
耳用のイヤークリームというものもあるので、クリームを使って綺麗にしてあげても問題ありませんよ。
イヤークリームとは、耳内の乾燥やべたつきを抑えてくれるクリームのことです。
殺菌効果も期待できるのでおすすめします。
4-3.洗浄液を使う
洗浄液は、耳の汚れがひどいときや、耳あかが溜まっているときに使います。
はじめに洗浄液を直接耳に垂らしてあげます。
多めに使用しても健康上は問題ありません。
続いて、耳の付け根あたりをよく揉んであげます。
すると耳あかが浮かんできて、中の汚れが徐々にとれてきます。
最後に、カット綿で、洗浄液を拭き取れば完了です。耳を傷つけないように、優しく拭き取ってあげましょう。
耳あかが溜まりやすいねこの場合は、通常の耳そうじにプラスして、洗浄液を使った耳そうじもしてあげると、耳内を常に清潔に保てます。
4-4.動物病院でしてもらう
耳そうじが上手くいかなかったり、ねこの様子がおかしいと感じたら、動物病院で診てもらうのが1番でしょう。
外耳炎や、耳ダニだった場合、適切な耳そうじに加えて、薬も処方してもらえます。
また、例えば、ねこが耳そうじを嫌がっている状況で、強引に耳そうじをしてしまうと、手前側にあった耳あかを、耳の奥に押し込めてしまう可能性があります。
L字構造になっていて耳そうじが難しいねこも、病院ならばしっかり耳そうじしてもらえますので、困ったらプロにお願いしましょう。
4-5.アロマオイルは使わない
アメリカの中毒管理センターのデータによると、ねこにティーツリーオイルを使用して中毒症状が出てしまったケースが2002年~2012年の10年間で106件もありました。
ティーツリーオイルとは、アロマオイルの一種です。
殺菌や香りづけ、耳そうじ時にねこにリラックスしてもらうためなど、使用用途はたくさんあると思いますが、決して使わないようにしましょう。
5.ねこが耳そうじを嫌がるときは

愛猫の耳あかが気になり、そうじをしようとしても嫌がるそぶりを見せる場合があります。
ずっとそうじをしないわけにもいきませんし、無理にそうじするのも良いか迷います。
判断が難しいですよね。どうすれば良いでしょうか。
5-1.無理やりそうじをしない
そうじをしようとして、嫌だと思ったのに無理やりされてしまったときの記憶は悪いものとして、ねこに残ってしまいます。
嫌がるそぶりをされたときに、強引にそうじをすると、耳かきが上手くいかず、内部を傷つけてしまう可能性があります。
無理やり抑え込んだり、力任せに耳を持ったりするのはやめましょう。
そうじができなそうだったら、またの機会にしてみることにするのが良いです。
どうしてもそうじをさせてくれないことが続くようであれば、動物病院の先生に相談してみるのがおすすめです。
5-2.触れ合う回数を増やす
耳そうじは、ねこがリラックスした状態でやるのが良いです。
愛猫と触れ合う回数を増やしてまず、より一層コミュニケーションをとることに注力しましょう。
顔や背中をなでる際に、耳に触る頻度を増やすことで、耳そうじを嫌がるリスクを減らしていきましょう。
また、極端に耳を触られることを嫌がる際は、耳の病気があるかもしれません。
まとめ
ねこの耳そうじは頻繁に行う必要がありません。基本的には週に1度耳そうじをしてあげる程度で大丈夫です。
耳がひどく汚れていたり、においがする、またかゆそうなそぶりが見られるときは、そうじしてあげましょう。
耳そうじを嫌がって出来ないなど。対応に困るようならば、動物病院で耳そうじをしてもらうのも手です。
- ねこがケガした、誤飲した!いざという時の応急処置を学ぼう
- 「ねこの血圧」徹底解説!測り方や血圧の数値から分かる病気を知ろう
- ねこのギネス記録!世界一の長寿や子だくさん、芸達者なねこはだれ?
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP1-10!定番からレア猫種までご紹介!
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP11-20定番からレア猫種までご紹介!
- ライフステージごとのねこの魅力!子ねこもシニアねこもみんなかわいい!
- FIP(猫伝染性腹膜炎)から愛猫を守ろう!予防法や治療法を解説
- ねこの毛の色が変わることってある?その理由とは
- 「内部寄生虫」あなたの愛猫は大丈夫?主な種類と症状、治療法を解説
- 雨の日、晴れの日、ねこはどうなる?天気ごとのねこのケアを解説!