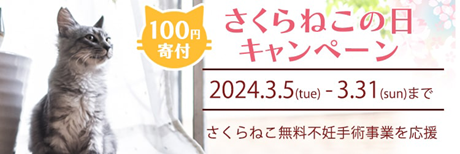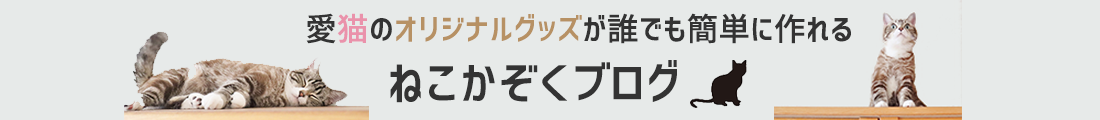
ねこにも帰巣本能はある!どうやって家までの道を知るの?

迷子になった犬が自分で家に戻ってきた、伝書鳩が何㎞も飛んで通信を運んだなど、動物は知らない場所に行っても、元のすみかに帰って来られる能力「帰巣(きそう)本能」を持っています。
ねこにももちろん帰巣本能はありますが、ずっと家に飼われているねこの帰巣本能は機能するのでしょうか。
また、ねこはどのように帰り道を知るのでしょうか。今回は、ねこの帰巣本能について解説していきます。
もくじ
1.帰巣本能とは2.ねこの帰巣本能の実験や調査
∟2-1.へリックの実験(1922年)
∟2-2.プレヒトの実験(1954年)
∟2-3.ダニエルによるアンケート調査(2013年~)
3.遠くから帰ってきたまいごねこたち
∟3-1.320㎞の道を帰ってきたホリー
∟3-2.引っ越し先の主人の家に現れたシュガー
∟3-3.長野から東京まで帰ってきたトラ
4.帰巣本能のしくみ∟4-1.体内時計
∟4-2.体内磁石
∟4-3.感覚地図
∟4-4.場所細胞(方向細胞)
まとめ
1.帰巣本能とは

帰巣本能(帰巣性)とは、動物が見知らぬ場所からすみかや食べ物のある場所に正確に戻ってくる能力のことです。
帰巣本能で有名な例としては、伝書鳩が挙げられます。伝書鳩はカゴに入れられ、遠い場所まで連れていかれた後で放たれます。もちろん、どのような道筋を通ってきたのか鳩には分かりません。
それでも鳩は数十㎞、時には数百㎞を飛び、正確に自分の小屋へと戻ります。
ねこにもこの帰巣本能があり、迷子になったねこが自力で帰ってきたという話も少なくありません。
ねこの帰巣本能はどの程度優れているのでしょうか。また、ねこはどうやって家までの道のりを知るのでしょうか。これから詳しくご紹介していきましょう。
2.ねこの帰巣本能の実験や調査

まずは、研究者が行ったねこの帰巣本能に関する実験や調査をご紹介します。
2-1.へリックの実験(1922年)
1922年、フランシス・H・ヘリックは、子ねこを生んだばかりの母ねこを使って帰巣本能の実験を行いました。
母ねこの子ねこに対する愛着は、家に帰る強い動機づけになります。そのため、帰巣本能の実験に母ねこが選ばれたのです。
ヘリックはねこを袋に入れて、車に乗せて遠い場所に運びました。そして、その場所で母ねこを袋から出し、子ねこの元へ戻れるかを実験したのです。実験場所から家までの距離は、最短1.6㎞、最長26.4㎞に設定され、全部で8回の実験が行われました。
その結果、母ねこは最初の7回までは無事に子ねこの元へ戻ることができましたが、最後の26.4㎞の道のりだけは帰ることができませんでした。
また、8回の実験のうち4回は、放たれてすぐに正しい方向に向かって歩き出したそうです。
しかし、この実験は100年前に行われたものであり、倫理的な面で非常に疑問が残ります。お乳を飲むくらいの小さな子ねこを母ねこから引き離すのは、残酷といわざるをえないでしょう。
2-2.プレヒトの実験(1954年)
こちらは、ねこが迷子にならないよう配慮がなされた帰巣本能実験です。
1954年、ドイツのプレヒトらは特別な迷路を使って帰巣本能に関する実験を行いました。
迷路には6方向に出口がついており、ねこがどの出口を選ぶかによって、家路への正確な方角を理解しているかどうかを読み取ろうとしたのです。なお、この迷路の出口は、ねこが出られないように工夫がしてありました。
その結果、迷路が自宅から5㎞の距離では、60%のねこがただしい出口を選ぶことができました。ランダムに選ぶのであれば正解率は1/6(16%)になりますので、意識して正しい出口を選んでいることが分かります。
また、結果には個体差があり、自宅と迷路の間を行き来した経験のあるねこは正解率が高く、研究室内で育てられたねこは成績が悪かったことも分かりました。
2-3.ダニエルによるアンケート調査(2013年~)
アメリカで「Lost Pet Research」という動物の捜索サービスを提供するサイトを運営しているダニエルは、2013年よりねこの帰巣行動に関するアンケート調査を行っています。
2018年7月に発表された中間報告によると、ねこの帰巣本能について以下のような結果が得られています。
- ・帰巣行動を示したねこのほとんどが外飼いもしくは外出OKのねこだった
- ・オスの方がメスより帰巣行動をより多く示した
- ・去勢・避妊手術をしていないねこは手術済のねこより帰巣行動をより多く示した
- ・ねこの性格と帰巣行動には関連性がない
- ・ほとんどのねこは5~7.5日で帰ってきた
- ・ねこの平均移動距離は2~4マイル(3.2~6.4㎞)だった
この調査は現在も続行しており、国外からでも回答ができます。興味のある方は、以下をご覧ください。
Lost Pet Research Cat Homing Behavior Survey Results
※「click here.」よりアンケート入力ページにジャンプできます。
3.遠くから帰ってきた迷子ねこたち

続いて、実際に遠くから帰ってきた迷子ねこたちのエピソードをご紹介します。
3-1.320㎞の道を帰ってきたホリー
素晴らしい帰巣本能を示したねことして有名なのは、フロリダ州のウエストパームビーチに住む三毛猫ホリーです。
2013年、当時4歳だったホリーは飼い主夫妻と一緒にフロリダ州の都市、デイトナに来ていました。そこでホリーは車から逃げ、行方不明になってしまいます。
しかし、それから63日後、ホリーは行方不明になった場所から320㎞も離れた自宅近くまで戻ってきたのです。体重は半分以下になり鳴くこともできないほど弱っていましたが、マイクロチップのおかげでホリーと分かり、無事飼い主夫妻と再会することができました。
保護された時、ホリーの爪や肉球はボロボロになっていました。これは誰かが連れて帰ったのではなく、自力で歩いて帰ってきた証拠であると考えられています。
3-2.引っ越し先の主人の家に現れたシュガー
アメリカの動物学者ワイルダーが紹介した、驚異的な帰巣性を持つねこ、シュガーのエピソードです。
シュガーの飼い主はカルフォルニアからオクラホマに引っ越す際、シュガーを隣人に譲りました。しかし、シュガーはすぐに姿を消し、1年2ヶ月後にオクラホマに住む元の飼い主の元にたどり着いたのです。シュガーはオクラホマの新しい家を知らないため、どのようにして飼い主を見つけたのかは謎に包まれています。
シュガーの歩いた距離はなんと2,400㎞。さらにその道のりには、ロッキー山脈や砂漠もあったということですから驚きです。
3-3.長野から東京まで帰ってきたトラ
日本国内でもねこが遠くからすみかに戻ってきたエピソードはいくつかあります。その中から、昭和53年(1978年)にあった「トラ」のエピソードをご紹介します。
トラは元気盛りの3歳のオスねこで、東京都武蔵野市のアパートで飼い主の女性と一緒に暮らしていました。
ある日、飼い主は結婚準備のためアパートを引き払い、トラと一緒に故郷の長野市に戻ることになりました。
しかし、引っ越しから3日後、トラはこつぜんと姿を消してしまいます。
それから5ヶ月後、トラはもとの家がある武蔵野市に戻ってきました。幸い、近くに住んでいた飼い主のお姉さんが見つけたため、無事に保護されました。
お姉さんが鳴き声に気づいて玄関のドアを開けたところ、嬉しそうに鳴きながら家の中に入ってきたそうです。
武蔵野市から長野市までの鉄道距離は233㎞ですが、トラはそれよりも長い距離を歩いたとも考えられています。
また、トラのケースは他のエピソードとは異なり、飼い主と一緒にいたにも関わらず、もとの家に戻っています。トラはオスねこですから、なわばりに強く執着したのかもしれません。
4.帰巣本能のしくみ

これまでご紹介してきた研究結果や実例から、ねこは住み家から離れても、その素晴らしい帰巣本能によって家に帰る能力があることが分かりました。それでは、ねこはどうやって家までの道のりを探し当てているのでしょうか。
帰巣本能のメカニズムはまだ解明されていない部分も多いのですが、特に有力な説を以下にご紹介します。
4-1.体内時計
体内時計とは、同じ場所に暮らすことでできる時間感覚のことです。すみかと違う場所に行った時、その場所の太陽の位置とすみかの太陽の位置の違いを感知し、そのズレを修正するように移動することで、すみかにたどり着けるといわれています。
4-2.体内磁石
人間を含め、動物は地球の磁場を感知する能力を持っています。これは「体内磁石」と呼ばれるもので、体の中に方位磁石を持っているようなものです。体内磁石は動物の組織内にある鉄の微粒子が関係しているといわれていますが、はっきりしたことは分かっていません。
4-3.感覚地図
動物には、視覚、聴覚、嗅覚などから得た情報から頭の中に一種の地図(感覚地図)を作り上げる能力があるといわれています。ねこにもこの感覚地図を作る力があり、それを使って家まで帰って来られると考えられています。
4-4.場所細胞(方向細胞)
場所細胞(方向細胞)とは、1990年にラットの脳内で発見された細胞です。1つの細胞が1つの場所を記憶し、その場所を通過した時だけ活性化されます。いわゆる脳のナビゲーションシステムのようなもので、ラットだけではなく多くの脊椎動物が持っていると考えられています。
まとめ
ねこの帰巣本能についてご紹介しました。ねこは鋭い感覚を持っており、遠く離れた場所から家までの道を探し当てる能力を持っています。
とはいえ、帰巣本能は絶対ではありません。あまりに距離が離れていたり、完全室内飼いで外の世界を知らなかったりすると、そのまま帰って来られないねこもいます。
ねこの帰巣本能は素晴らしいものですが、それに頼らず、ねこが迷子にならないように気をつけましょう。
- ねこがケガした、誤飲した!いざという時の応急処置を学ぼう
- 「ねこの血圧」徹底解説!測り方や血圧の数値から分かる病気を知ろう
- ねこのギネス記録!世界一の長寿や子だくさん、芸達者なねこはだれ?
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP1-10!定番からレア猫種までご紹介!
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP11-20定番からレア猫種までご紹介!
- ライフステージごとのねこの魅力!子ねこもシニアねこもみんなかわいい!
- FIP(猫伝染性腹膜炎)から愛猫を守ろう!予防法や治療法を解説
- ねこの毛の色が変わることってある?その理由とは
- 「内部寄生虫」あなたの愛猫は大丈夫?主な種類と症状、治療法を解説
- 雨の日、晴れの日、ねこはどうなる?天気ごとのねこのケアを解説!