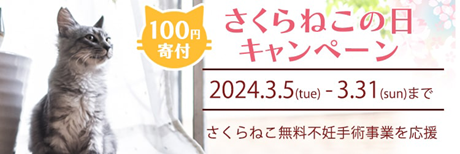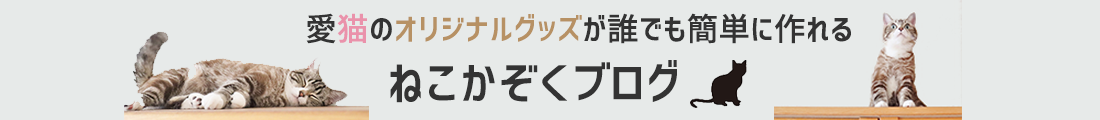
猫パルボウイルス感染症って?治療法、予防法、消毒の注意点まで紹介

猫パルボウイルス感染症をご存知ですか?以前は、猫ジステンパーと呼ばれていた病気です。
猫パルボウイルス感染症は、感染力が強く、致死率が高いとてもおそろしい感染症と言われています。そのため、獣医師がもっとも嫌う病気でもあります。
今回は、そんな猫パルボウイルス感染症の基礎から予防法、消毒の際の注意点までくわしく解説します。
目次
1.猫パルボウイルス感染症とは
∟1-1.猫パルボウイルス感染症ってどんな病気?
∟1-2.猫パルボウイルスの感染経路
∟1-3.猫パルボウイルス感染症の症状
2.猫パルボウイルス感染症の治療
3.猫パルボウイルスの感染予防と対策
∟3-1.ワクチン接種で感染予防
∟3-2.多頭飼いの場合は隔離を徹底する
4.猫パルボウイルスの消毒についての基礎知識
∟4-1.効果的な消毒薬は?
∟4-2.消毒の際の注意点
まとめ
1.猫パルボウイルス感染症とは
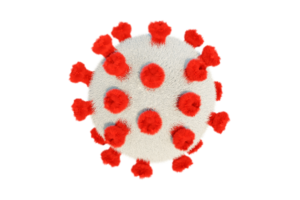
猫パルボウイルス感染症とは、猫パルボウイルスの感染によって引き起こされる感染症です。
2018年に東京都立川市の猫カフェで集団感染が発生し、管理が杜撰(ずさん)だったこともあいまって大問題になりました。
このできごとをきっかけに「パルボ」という名前を知った飼い主さんも多かったようです。
では、猫パルボウイルス感染症とはどのような病気なのでしょうか?
1-1.猫パルボウイルス感染症ってどんな病気?
猫パルボウイルス感染症は、「猫伝染性腸炎」や「猫汎白血球減少症」とも呼ばれており、以前は「猫ジステンパー」と呼ばれていました。
感染力が非常に強く、ワクチンをしておらず免疫を持っていないねこは、ほぼ100%感染します。しかも子猫が感染した場合の致死率は75〜90%といわれています。
さらにやっかいなことに、猫パルボウイルスは非常に安定しているウイルスで、環境中では3年、外気温30度以上でも数ヶ月生存することが可能だと言われています。また、室温以下では1年以上も感染性があることが分かっています。
そのため、保護猫活動をしている人たちや獣医師の間でも非常に恐れられている感染症のひとつとなっているのです。
1-2.猫パルボウイルスの感染経路
猫パルボウイルスの感染経路は非常に多岐に渡ります。主要な感染経路だけでもこれだけあります。
- ・感染したねこの排泄物
- ・感染したねこの唾液
- ・食器やおもちゃなどの共有
- ・カーテンやカーペットなど
- ・ノミが媒介
- ・人間が媒介
とくに注意したいのは、感染しているねこ同士の接触です。
感染力が非常に強く、多頭飼いをしている場合は一気に感染が広がるおそれがあります。猫パルボウイルスに感染したねこは、症状が出る3日前からウイルスを排出するといわれていますので、気づかないうちに感染が広まってしまう可能性があります。
また、お外にお出かけするねこは、野良猫のうんちやおしっこから感染する危険性を考慮しなければいけません。
そのほか、見落としがちなのは、人間が媒介者になっていることです。服やバッグ、靴の裏などにウイルスが付着して間接的に感染することもあります。
神経質になりすぎる必要はないと思いますが、野良猫と触れ合ったり、ペットショップなどのねこのいる場所を訪問したりしたあとは念のため注意しましょう。
1-3.猫パルボウイルス感染症の症状
パルボウイルス潜伏期間は、数日〜2週間ほどです。発症すると、初期症状では以下のような症状があらわれます。
- ・発熱
- ・食欲不振
- ・元気がない
- ・腹痛
- ・嘔吐
- ・下痢
- ・脱水症状
初期症状としては、40〜41度の発熱、元気がない、食欲不振といった症状があらわれます。そして、発熱から1〜2日後には、下痢、嘔吐、脱水といった症状が見られるようになります。
発症から5〜7日ほどで亡くなることも多く、とくに免疫力の弱い低月齢の子猫は、発症後12時間以内に亡くなってしまうことも少なくありません。
発症してから5日間を無事に乗り越えると数日から数週間で回復する見込みが高いと言われています。
また、重症化すると以下の症状が見られます。
- ・白血球の減少
- ・貧血
- ・下痢
- ・血便
- ・脱水
白血球の減少による細菌の二次感染で敗血症をおこし亡くなるケースもあります。
2.猫パルボウイルス感染症の治療

猫パルボウイルスに対する抗ウイルス薬はありませんので、下痢や嘔吐、脱水などの症状を抑える対症療法をおこなうことになります。
また、場合によっては免疫力を高めるためにインターフェロンを投与する場合もあります。
猫パルボウイルスは、発症後すぐに治療を開始し、重症化を防ぐことができれば、回復する見込みのある病気です。回復すれば、後遺症もなく普通の暮らしを送れるようになります。
3.猫パルボウイルスの感染予防と対策

猫パルボウイルスから愛猫を守るいちばんの方法はワクチンを接種することです。
不幸にも、多頭飼いで感染が発生した場合は隔離と消毒を徹底して感染を広げないようにしましょう。
3-1.ワクチン接種で感染予防
猫パルボウイルス感染症はワクチン接種で予防することができます。
猫パルボウイルスのワクチンは、コアワクチンのひとつなので、3種混合ワクチンにも含まれています。
年1回の接種で愛猫の命を守ることができます。人間が媒介者になることもありますので、完全室内飼いであっても接種しましょう。
ただし、まれに抗体ができないねこもいますので、ワクチンを接種しても感染しているねことの接触は避けなければいけません。
3-2.多頭飼いの場合は隔離を徹底する
多頭飼いの場合は感染を拡大させないためにも、感染したねこの隔離を徹底してください。
とくに、以下の点に注意しましょう。
- ・感染したねこと触れ合わない
- ・部屋を完全にわける
- ・感染したねこが使用したものは絶対共有しない
- ・人間を介した感染対策を徹底する
感染したねこが使用した食器やおもちゃ、ベッド、トイレの共有は絶対に避けなければいけません。もったいないと思うかもしれませんが、処分することをおすすめします。
また、ねこの看病をしている人間が媒介者になる可能性もありますので行動には十分に注意してください。
回復したあとも最長で6週間程度に渡って、うんちやおしっこにウイルスが排出される可能性があります。しばらくは、隔離をつづけ、トイレなどの共用も避けるようにしましょう。
4.猫パルボウイルスの消毒についての基礎知識

猫パルボウイルスは消毒もやっかいなウイルスです。一般的な消毒薬では効果がありませんし、やり方を間違えればかえって感染を広げてしまうかもしれません。
猫パルボウイルスに効果的な消毒薬と消毒の注意点を紹介します。
4-1.効果的な消毒薬は?
猫パルボウイルスは、一般的なアルコール消毒、アンモニア消毒、煮沸消毒では効果がありません。
猫パルボウイルスに効果があるとされているのは以下の消毒薬です。
- ・過酢酸
- ・二酸化塩素
- ・水酸化ナトリウム
- ・次亜塩素酸ナトリウム(6%)
- ・ホルムアルデヒド(4%)
- ・グルタルアルデヒド(1%)
- ・ペルオキシ一硫酸カリウム
おすすめは、次亜塩素酸ナトリウムです。ハイターやキッチンハイターにも含まれており、希釈することで消毒薬として使用することができます。
4-2.消毒の際の注意点
消毒をする際は、ウイルスの付着を防ぐために、ビニール製の手袋や雨ガッパ、足カバー、キャップなどを使用し完全防備で行なうことをおすすめします。
消毒時に使用した雨合ガッパや雑巾などは、すべて1回ごとに捨てて、毎回新しいものを使用します。
感染したねこが使用している部屋のカーテンやカーペットなど消毒が難しいものは、残念ですが処分することをおすすめします。また、床や壁、家具、など処分することができないものは、すべて拭いて消毒をしてください。
着ていた服は、消毒液につけて消毒をしてから洗濯をします。最後に、シャワーを浴びるなどして、体に付着しているかもしれないウイルスを落とします。
「かなり面倒くさいな」と感じるかもしれませんが、猫パルボウイルスはここまでやらなくてはいけないほどの怖いウイルスなのです。
まとめ
猫パルボウイルスは感染力が強く、致死率も高いため大変恐ろしい感染症とされています。
とくに、多頭飼いで発生した場合はあっという間に感染が広がってしまいます。もし猫パルボウイルスのような症状が見られ、心当たりがあるならば、すぐに隔離し、早急に動物病院を受診しましょう。
猫パルボウイルス感染症は、ワクチンで予防することのできる病気です。定期的にワクチンを受けさせることで、愛猫の命を守ることができます。獣医師と相談し、忘れずに接種するようにしましょう。
3.猫パルボウイルスの感染予防と対策

- ねこがケガした、誤飲した!いざという時の応急処置を学ぼう
- 「ねこの血圧」徹底解説!測り方や血圧の数値から分かる病気を知ろう
- ねこのギネス記録!世界一の長寿や子だくさん、芸達者なねこはだれ?
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP1-10!定番からレア猫種までご紹介!
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP11-20定番からレア猫種までご紹介!
- ライフステージごとのねこの魅力!子ねこもシニアねこもみんなかわいい!
- FIP(猫伝染性腹膜炎)から愛猫を守ろう!予防法や治療法を解説
- ねこの毛の色が変わることってある?その理由とは
- 「内部寄生虫」あなたの愛猫は大丈夫?主な種類と症状、治療法を解説
- 雨の日、晴れの日、ねこはどうなる?天気ごとのねこのケアを解説!