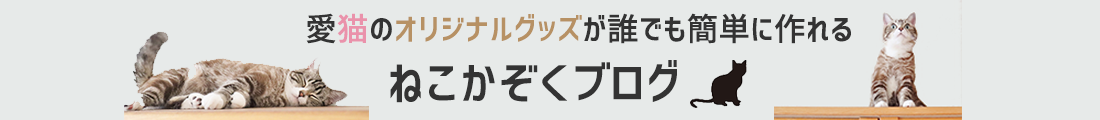
古今東西、小説家はねこが好き!ねこ好きの小説家をご紹介

ねこはその優美な姿、可愛らしい容姿やしぐさ、そしてそこに隠された気まぐれさや神秘性から、人の心をとらえ続けています。
そしてそんなねこの魅力は、古今東西問わず数多くの小説家によって、物語に書き記されています。
今回の記事では、ねこ好きの小説家と、彼らとねことの関わりについてご紹介します。
目次
1.【海外】ねこ好きの小説家
∟1-1.アーネスト・ヘミングウェイ
∟1-2.ポール・ギャリコ
∟1-3.エドワード・ゴーリー
2.【日本近代】ねこ好きの小説家
∟2-1.夏目漱石
∟2-2.内田百聞
3.【日本現代】ねこ好きの小説家
∟3-1.村山由佳
∟3-2.角田光代
まとめ
1.【海外】ねこ好きの小説家

まずは海外のねこ好きな小説家をご紹介します。
エピソードに登場するねこたちはみんな風変わりですが、だからこそ愛しくおもしろい子ばかりです。
1-1.アーネスト・ヘミングウェイ
アーネスト・ヘミングウェイ(1899年~1961年)はアメリカの小説家です。
代表作としては「老人と海」や「武器よさらば」「誰がために鐘は鳴る」などが有名ではないでしょうか。
ねこ好きだったヘミングウェイは、ある日2匹のねこをもらいます。
そのねこたちは遺伝子変異により足の指が6本ありました。ヘミングウェイは幸運を呼ぶねこと信じ、一緒に暮らし始めます。
そしてこのねこたちは本当に「幸運を呼ぶねこ」でした。
ねこたちを飼い始めてから書き上げた小説「老人と海」が大ヒットし、ノーベル文学賞を受賞するに至ったのです。
1961年にヘミングウェイが亡くなった後、米フロリダ州にある彼の邸宅は博物館へと生まれ変わりました。
そこには、「幸運を呼ぶねこ」の子孫である、6本指のねこたちが暮らし続けています。
1-2.ポール・ギャリコ
ポール・ギャリコ(1897年~1976年)はアメリカの小説家です。
代表作は「スノー・グース」。人間嫌いの男性と少女、そして傷ついた白雁が織りなす幻想的で切ない物語です。
ギャリコはねこが主人公の作品も書き残しています。
主人公の少年がねこになって冒険に出かける「ジェニイ」や、ねこが人間をしつけるノウハウを記したとされる「猫語の教科書」などが有名です。
いずれの作品も、まるでギャリコがねこにインタビューをしたか、もしくはギャリコ自身がねこだったのではないかと思われるような、生き生きした筆致でねこの姿や考えが描かれています。
ポール・ギャリコの写真のひとつに、2匹のねこと撮ったものがあります。
1匹はギャリコに抱かれ、もう1匹はギャリコの着ているコートのフードの中に納まっています。
2匹とも満足そうな表情をしており、ギャリコとの絆が感じられます。
1-3.エドワード・ゴーリー
エドワード・ゴーリー(1925年~2000年)はアメリカの絵本作家です。
彼が書く絵本は「絵本」の範疇を超えた、不条理さや残酷さがあふれるものが多く、見る者に強い印象を与えます。
ねこ好きだったゴーリーは、自分の作品にもたくさんのねこを登場させました。
しかし、そのねこたちは愛嬌があり、のんきそうで、他の登場人物たちのような残酷な目に遭うことはありませんでした。
ゴーリーのねこたちは、飼い主の画板の上に寝転ぶのが大好きだったそうです。
背筋の凍るような恐ろしいストーリーを描くゴーリーが隠し持つ優しさや繊細さを、ねこは感じ取っていたのかもしれません。
2.【日本近代】ねこ好きの小説家

海外のみならず、日本においても、ねこは昔から芸術や文学のモチーフとなってきました。
日本近代を彩る小説家たちの中にも、数多くのねこ好きがいます。特に有名な小説家とそのエピソードをご紹介します。
2-1.夏目漱石
日本で「ねこ」の小説といえば、まずまっさきに浮かぶのが夏目漱石の「吾輩は猫である」ではないでしょうか。
「吾輩は猫である。名前はまだない」という鮮烈な出だしから始まる、猫の視点から見た人間模様を描いたこの小説は、またたく間に大ヒットし、日本史上に残るベストセラーになりました。
主人公のねこのモデルは、漱石の家に迷い込んできた野良猫だといわれています。
漱石は犬には「ヘクトー」という立派な名前を付けましたが、このねこは最後まで「ねこ」と呼んでいたそうです。
ねこが亡くなった時は、墓標に「この下に稲妻起る宵あらん」という一句を添え、近しい人にねこの死亡通知を出したという話が残されています。
しかし、夏目漱石は生前、「ねこは好きじゃなく、犬の方が好き」と語っていたそうです。
また、漱石夫人はむしろねこ嫌いだったともいわれています。
しかし、「ねこ」が亡くなった時に墓標を用意したのは漱石夫人でした。
また命日には忘れずに鮭とかつおぶしをお供えしていたそうです。
これらのエピソードはねことの別れを描いた漱石の随筆「猫の墓」で語られています。
このような随筆を書くところから考えても、漱石自身もたとえねこ好きではなかったとしても、ねこを特別な存在だと感じていたのかもしれません。
2-2.内田百聞
内田百閒(1889年~1971年)は、日本を代表するペットロス小説といえる「ノラや」を書いた小説家として知られています。
百閒はもともとねこが好きだったというわけではないのですが、ある日家に迷い込んできたねこを「ノラ」と呼んで溺愛するようになります。
しかし、ノラは来た時と同じように、ある日突然いなくなってしまいました。
百閒はノラを探して二万枚近くのチラシを配り、新聞広告を出し、外国人向けに英語のポスターまで作りました。
しかしノラは見つからず、百閒は強い悲しみに打ちのめされます。
このエピソードを日記形式で描いたのが「ノラや」です。
百閒は原稿を読み返すのが辛く、校正ができなかったといわれています。
3.【日本現代】ねこ好きの小説家

続いて現代活躍しているねこ好きの小説家たちをご紹介します。
エッセイやWEB、SNSなどでそのかわいい姿を見ることもできますので、興味が湧いたら探してみるのも良いかもしれません。
3-1.村山由佳
村山由佳(1964年~)さんは「星々の舟」や「ダブル・ファンタジー」、2021年には「風よ あらしよ」で第55回吉川英治文学賞受賞を受賞するなど、次々とヒット作を生み出しています。
そんな村山さんは、愛猫を描いたエッセイを数多く執筆している「ねこ好き」の小説家としても有名です。
特に愛したのが、メスの三毛猫「もみじ」です。
もみじは村山さんの飼っていたねこ「真珠」の子供でした。真珠の陣痛が始まった際、村山さんは真珠の手を握り、その出産を見守りました。
生まれた4匹の子猫のうち、一番小さな末っ子が「もみじ」でした。
もみじは引っ込み思案で村山さんしか懐きませんでした。
そのため、当時の夫と別れて家を出る際に、もみじだけを連れて行ったそうです。
もみじは村山さんとともに過ごし、人生を見守ってきました。
村山さん自身も、「もみじほど、私の魂の間近にまで寄り添ってくれた猫はいない」(前掲書)と語っています。
もみじは2018年に17歳10ヶ月の生涯を閉じました。村山さんのTwitterにはもみじと過ごした愛猫「銀次」や「サスケ」が愛らしい姿で登場します。
そして時々は「もみじ」の思い出も、そっと描かれます。
「細いほそい三日月を見ると、もみじを喪った日のことを思い出す。寂しいけれど、たくさん思い出せるのはきっと幸せなことよ。」(Twitter 村山由佳(時々もみじ) 2022年1月5日のツイートより)
3-2.角田光代
「八日目の蝉」や「対岸の彼女」を著した角田光代(1967年~)さんも、ねこ好きの作家として知られています。
特にねこ好きではなく、ねこを飼ったこともなかった角田さんにねこをあげたのは、漫画家の西原理恵子でした。
譲り受けたメスのアメリカンショートヘアは「トト」と名付けられ、角田さん夫妻と一緒に住み始めます。
トトは寛容で優しい性格ですが、少し主張が弱いところがあります。
角田さんはそんなトトの性格を「じっとり」と表現し、「自分と夫に似ている」と感じたそうです。
角田さんはトトとの生活をこう語っています。
「トトが来て、何か自分以外のことに心を持っていけるようになったことが、自分にはすごく良かった」(「NHK ネコメンタリー 猫も、杓子も。物書く人のかたわらには、いつも猫がいた」河出書房新社発行 2019年)
自分自身と向き合い、時に追い詰めてしまう小説家という仕事において、トトはその苦しい心の栓を抜いてくれる存在なのかもしれません。
まとめ
ねこ好きの小説家たちをご紹介しました。
気ままでいたずらっ子なねこたちですが、人の心に寄り添い、慰めてくれるさりげない優しさも持ち合わせています。
自分自身の魂を削って作品を作り上げる小説家たちにとって、ねこの存在は限りない癒しとなり、インスピレーションの源になったに違いありません。
今回の記事をお読みになって気になる小説家がいたら、ぜひ作品も読んでみてください。
同じ「ねこ好き」同士、心がつながるような素敵な出会いになるかもしれません。
- ねこがケガした、誤飲した!いざという時の応急処置を学ぼう
- 「ねこの血圧」徹底解説!測り方や血圧の数値から分かる病気を知ろう
- ねこのギネス記録!世界一の長寿や子だくさん、芸達者なねこはだれ?
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP1-10!定番からレア猫種までご紹介!
- 【2024年度最新】猫種人気ランキングTOP11-20定番からレア猫種までご紹介!
- ライフステージごとのねこの魅力!子ねこもシニアねこもみんなかわいい!
- FIP(猫伝染性腹膜炎)から愛猫を守ろう!予防法や治療法を解説
- ねこの毛の色が変わることってある?その理由とは
- 「内部寄生虫」あなたの愛猫は大丈夫?主な種類と症状、治療法を解説
- 雨の日、晴れの日、ねこはどうなる?天気ごとのねこのケアを解説!



