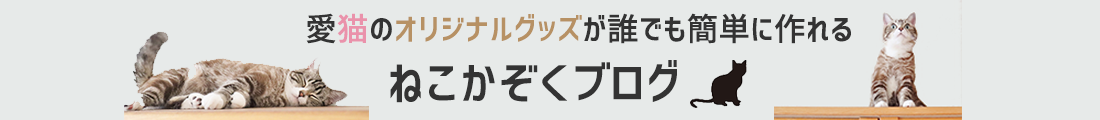
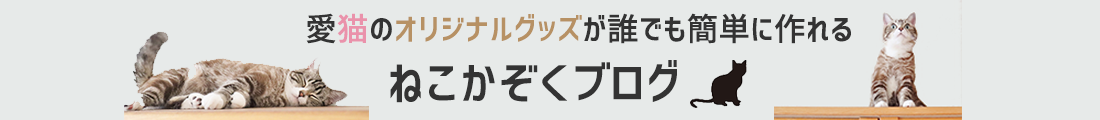

猫カフェなら聞いたことはあるけど、保護猫カフェっていったいどういうところなの?
猫カフェと保護猫カフェ。何か、特別な違いがあるの?
など、率直な疑問をお持ちの方はきっと多いことでしょう。
ここでは、猫カフェと保護猫カフェの違いや、保護猫カフェの目的、運用などについて解説していきます。

猫カフェも保護猫カフェも、ねこと触れ合うことのできる癒やし系の場所であることについて大きな違いはありません。
ただ、ねこがいるカフェのではありますが、カフェ設立の目的やカフェの運用などシステムが違うのです。
猫カフェとは、飲食店としての形態を残しながら、店内に数匹のねこを放し飼いにし、カフュを訪れる客が、同じ空間の中でねこに癒されるのを売りに経営されているカフェのことをです。
カフェでは、ねこと触れ合いながら飲食も可能ですが、ほとんどのお店ではソフトドリンクのみのサービスが一般的になっています。
お店の形態としては、猫カフェも保護猫カフェもほとんどの違いはありません。
一般的な猫カフェのねこは、お店のオーナーの飼い猫や店舗で飼っているねこです。
一方、保護猫カフェのねこは、飼い主から捨てられたねこや、もともと野良猫をあったねこを、カフェで保護しているねことなります。
保護猫カフェのねこは、里親探しが目的のものであり、新しい飼い主となる人との出会いをお店で待っていることが猫カフェとの大きな違いでしょう。
猫カフェが猫フアンの癒しの場なら、保護猫カフェは、ねこの命を助けるためのボランティア活動の拠点といえるでしょう。
ねこの保護団体が里親探しのために、沖縄にオープンさせたのが保護猫カフェの始まりだといわれています。
保護猫カフェは、近年、犬猫の殺処分が社会問題としてクローズアップされてきたことを背景に、野良猫や捨て猫の命を少しでも救ってあげたいというボランティア活動から生まれたものなのです。
このボランティアから生まれた保護猫カフェは、全国的に波及していつの間にか地方都市にまで浸透してきました。

猫カフェは、営利目的の店舗であるのに反して、保護猫カフェは、保護したねこを里親へと譲渡することを目的とした、非営利目的の店舗が主流です。
しかし、いくら利潤を追求しない店舗だとしても、店舗をオープンし維持管理するためには多大なコストがかかります。
保護猫カフェをオープンするためには、店舗となる家屋が必要になります。
自分で所有する家屋であれば問題はないですが、賃貸となると場所によっては多くの費用がかかるでしょう。
また、保護猫カフェ仕様に店舗を改築するとか、ねこを飼うためのさまざまな用具や遊具を準備しなければなりません。
ねこを飼ってみればよく分かることですが、一頭のねこを飼うにも多くの費用がかかります。
たとえば、食費です。
食費の他にも、トイレの猫砂代やシャンプー代、爪とぎ用の用具代などあげて行けばきりがありません。
いちばん費用がかかるのは、何と言っても医療費です。
特に、伝染病予防のためのワクチン接種や避妊のための避妊手術や去勢手術などねこを飼うためにはいろいろな費用がかかるのは覚悟しなければなりません。
このように、保護したねこを店舗で飼うことになったら、里親にねこを譲渡するまでに支出する食費や医療費など、予想以上のコストがかかることは珍しいことではありません。
ましてや、保護猫をカフェで多頭飼いすることになれば、費用は倍、倍に増えることになるでしょう。
保護猫カフェの運営は、家族のみのスタッフであるとか、趣旨に賛同する友人同士など、2~3人のスタッフが働いている場合がほとんどです。
金銭的に従業員を雇う余裕がありません。
また、少ないスタッフでカフェを賄うことは大変です。
カフェの中ではねこたちの健康状態や食事、掃除、来客への対応、譲渡に関する電話での応対など、それこそ猫の手も借りたいほど忙しく、時間的に余裕のないものになっています。
スタッフの不足が懸念される問題です。
保護猫カフェは、猫カフェと比べるとまたまだ認知不足です。
保護猫カフェも、猫カフェとなんら違いはないと思って、カフェを訪れるお客も多いと聞いています。
そのお客のほとんどは、ねこに癒されることを目的にカフェを訪れる訳ですから里親になることにはあまり関心を示しません。
これでは、保護猫カフェの里親制度や譲渡などの本来の目的を達することはできないでしょう。

すでに述べましたように、保護猫カフェを経営するに当たっては多くの資金を必要とします。
また、収入がなければ経営はたちまち成り立たなくなります。
カフェの収入は、カフェを訪れるお客の入場料と譲渡に伴う一部の収入だけが頼りです。
カフェを訪れるお客の入場料は、ドリンク代を含めても、1,000~1,500円というところがほとんどです。
これでは、よほど、回転率を上げなければ経営は大赤字となってしまいます。
営利目的の猫カフェでさえ、経営はなかなか成り立たないと言われる中にあって客単価の安い現状では経営を続けていくのは難しいことでしょう。
多くの保護猫のスタッフは、獣医師のようにペットなど動物に関することを詳しく学習し知識としている訳ではありません。
ねこの里親となりたいお客から、ねこの飼い方や、病気などの対応について尋ねられたら、迷わず、的確なアドバイスが行えるなどの対応が求められてしまいます。
ペットについての専門的な知識が求められますが、スタッフは専門家ではないため、回答が出来ない場合があります。
コロナ禍の影響は、保護猫カフェにも及んできています。
ほとんどの、飲食店が営業の自粛を強いられている中で、経営そのものにも暗雲が立ち込め始めました。
ここにきて、これ以上の営業をあきらめてカフェをたたむ経営者も増えてきています。

ペットブームの高まりで、ペットを飼う飼い主が増えてきています。
特に最近は、犬よりも、ねこを飼いたいと思う人が増えてきています。
コロナ禍でもペット人気は下がることなく、多くの人が癒しを求めて、ねこを飼うという事例が多く見られるようになりました。
しかし、問題は飼い主が、最期まで飼い猫の面倒を見るかということなのです。
せっかく、求めたねこを、簡単に遺棄してしまうという飼い主の行為が社会問題にもなっています。
飼い主から捨てられてしまったねこは、いったいどこへ行けばいいのでしょうか。
捨てられてしまったねこは、運よく新しい飼い主に迎えられればいいのですが、ほとんどのねこは野良猫となって厳しい世界で生きて行かなければなりません。
地域の行政が主導する、愛護センターなどで月に1回程度譲渡会を開いて保護猫の里親探しをしています。
しかし、保護される野良猫や捨て猫の数が多すぎて、里親探しがなかなかうまく機能していないのが現状です。
そこで、里親探しの有効な手段となるのが、これまで紹介してきた民間の主導する保護猫カフェの存在です。
家族の一員として、あたたかく迎え入れられたはずのペットが飼い主の気紛れから簡単に遺棄されています。
野良猫や捨て猫も、そんな飼い主のエゴやモラルのなさから遺棄されたものです。
野良猫や捨て猫は、新しい飼い主が見つからない限りは、自分で生きていくか、殺処分されていく運命にあります。
こんな酷く可哀そうなことが許されていい訳がありません。
殺処分ゼロの道のりはそう簡単なものではありません。
この機会に保護猫カフェの意義とシステムをよく理解して、ねこの殺処分ゼロに向けてみなさんの協力をお願いいたします。