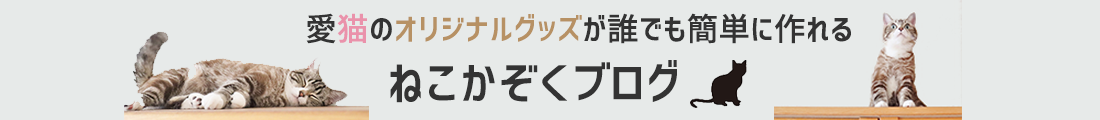
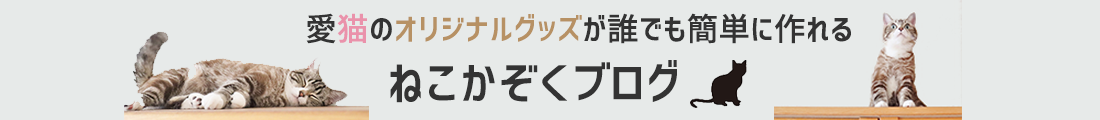

保健所や動物愛護センターでのねこの殺処分の数が、犬を上回っているという事実をご存知でしょうか。
近年のねこブームの影では、そのような悲しいことが起こっているのです。
なぜ、ねこの殺処分は多いのでしょうか。また、ねこの命を守るために、私たちには何ができるのでしょうか。
今回はねこの殺処分問題と、その対策について解説します。

まずは、現在のねこ・犬の殺処分の状況についてご紹介します。
環境省が発表した「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」によると、2020年4月1日~2021年3月31日の犬猫の引取り及び処分の状況は以下のようになっています。
| 引き取り数 | 殺処分数 | 殺処分数/
引き取り数 |
|||||
| 全体 | うち 幼齢の個体 (%は全体に占める割合) |
全体 | うち 幼齢の個体 (%は全体に占める割合) |
||||
| ねこ | 44,798 | 30,879 | 68.9% | 19,705 | 13,030 | 66.1% | 44.0% |
| 犬 | 27,635 | 5,238 | 19.0% | 4,059 | 806 | 19.9% | 14.7% |
※「引き取り数」は施設に持ち込まれたねこ・犬の数を指します。
※「幼齢の個体」とは主に離乳していない個体を指します。
また、成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体については、すべて成熟個体として計上しています。
このようにねこは犬よりも引き取り数が多いうえ、殺処分される割合も高く、犬を大きく上回っています。
その数はなんと年間2万頭にも上ります。
そんなたくさんのねこたちが、悲しい最期を迎えているのです。

それではなぜ、ねこの殺処分は引き取り数も多く、殺処分の割合が犬より多いのでしょうか。
その主な理由について解説します。
先ほど触れたとおり、施設に連れてこられたねこ・犬の内訳を見ると、ねこの方が犬より圧倒的に幼齢の個体(赤ちゃん)が多いことが分かります。
その割合はなんと全体の60%です
成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体は、全て成熟個体として計算に入れているところもあります。
そのため施設に連れてこられ、殺処分された子猫の数はもっと多いと考えられるでしょう。
ねこはとても多産な生き物です。
春~秋を中心に、1年に2~3回発情期を迎えます。
また交尾によって排卵が誘発されるため、交尾をするとほぼ100%の確率で妊娠します。
1回に産む赤ちゃんの数も多く、2~5匹くらい出産します。
さらに、メスは生後半年~1年程度で子猫を産めるようになるため、産んだ子猫がまた子猫を産みというように、それこそ「ネズミ算式」にねこが増えていきます。
避妊手術をせずにメスねこを飼った場合、数年で数十匹まで増えてしまう場合もあり、飼いきれずに保健所に連れて行ってしまうというケースもあります。
町を歩いていると、野良猫は時々目にしても、野良犬はあまり見ないかもしれません。
野良犬は狂犬病予防法により飼い犬の登録が義務づけられ、野良犬を捕獲できる仕組みができているためです。
しかし、ねこは捕獲の仕組みがないため、町や公園で野良猫として生活しています。
ねこは「動物の愛護及び管理に関する法律」により愛護動物と定められており、むやみに捕獲できません。
そのねこたちに「餌やりさん」がご飯をあげることで、どんどん増えてしまい、結局は多くの殺処分に繋がってしまうという悲惨な結末を迎えてしまう場合もあります。
先ほどの「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」によると、施設に連れてこられる犬の90%が飼い主以外からの持ち込みとなっています。
そのため返還数も多く、2020年度には9,463匹の犬が飼い主のもとに帰れています。
それに対し、ねこの飼い主以外からの持ち込みは約77%程度、つまり23%は飼い主による持ち込みです。
返還数も少なく、2020年度に飼い主のもとに帰れたねこは255匹のみです。
このように、ねこは飼い主が連れてくる割合が犬より多いため、返還数が少なく、殺処分が多くなるのです。
犬は庭につなぐか、もしくは室内で飼育し、散歩のときだけ外出するという飼い方がほとんどです。
しかし、ねこは自由に放し飼いをしている人も少なくありません。
出かけた先で妊娠し、野良猫を増やしてしまうこともありえます。
先ほどご紹介したとおり、ねこは赤ちゃんをたくさん産む動物です。
さらに、犬とは違い、狭いところや高いところに入り込めるため、知らないうちに妊娠し子猫を産んでいたということもあります。
特に完全室内飼いではない状態で、避妊手術をしていない場合は、ねこの状況を把握しきれず、気づくと多頭飼育崩壊に陥ってしまっているという場合もあります。

せっかく産まれて来た大切な命を、殺処分という悲しい目にあわせないようにするために、私たちにはどのようなことができるでしょうか。
ねこの殺処分を減らすための方法をいくつかご紹介します。
ねこを飼うのであれば、繁殖を望むと強く考えている場合以外は避妊手術、去勢手術を検討しましょう。
「健康なのに手術をするのはかわいそう」「子供を産む体験をさせてあげたい」と思われる方もいらっしゃいますが、もし産ませるのであれば、生まれた赤ちゃんたちが幸せになれるよう手を尽くさなくてはなりません。
そのためには必ず引き取り先を予め決めておく必要があります
避妊手術をすることで、発情期の脱走や子宮・卵巣の病気を防止できます。
オスの場合は去勢手術により、スプレー(縄張りつけのためにおしっこをかける)を減らせます。
人とねこが快適に、安全に過ごすためにも大切な手術であるといえます。
今飼っているねこを迷子にさせないよう、室内飼いを徹底しましょう。
窓や扉から出ないように、脱走対策を進めてください。
また、もし迷子になってもいいように、マイクロチップの装填をするのも有効な手段です。
※令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーなどで販売される犬やねこについて、マイクロチップの装着が義務化されました。
ねこを迷子にさせないことで、大切なねこの命を守り、不幸なねこが増えるのを防げます。
ねこだけではなく、動物を飼ったら、その動物の命が尽きるまで責任を持って飼わなくてはなりません。
しかし、高齢や病気、事故のために飼えなくなるというケースもあります。
そのため捨てられたり、保健所に持ち込まれたりと、不幸なねこが増えてしまうことになります。
それを防ぐためには、自分に万が一のことがあった場合のねこの行き先を考えておかなくてはなりません。
引き取ってくれる家族や友人がいるなら安心ですが、それが難しい場合は「ペットあんしんケア制度」や「ペット信託」の利用を検討するのもひとつの手段です。
かわいいねこが近づいてくると、ついご飯をあげたくなります。
しかし、野良猫にご飯をあげることでその場に住みついてしまい、子猫を産み、野良猫が増えることになります。
野良猫を「かわいそう」と思うのであれば、自分で責任を持って保護して飼うという覚悟を持たなくてはなりません。
それが難しい場合は、野良猫を保護するボランティアに参加する、寄付をするといった形でねこを助けることもできます。
※ねこかぞくブログ「捨て猫を見つけた時に何をすべきか」を参考にしてください。
野良猫や保健所に持ち込まれたねこを助けるための活動をしているボランティアやNPO法人も数多くあります。
そうした活動に参加することで、ねこの殺処分を減らることに繋がるでしょう。
保護活動としては、保護したねこが人との生活に慣れるための「一時預かり」や、赤ちゃんねこにミルクをあげる「ミルクボランティア」などがあります。
責任は重いですが、かわいいねこに癒されながら命をつなぐ活動ができます。
活動が難しい場合は、寄付による支援もできます。
寄付はお金だけではなく、あまったフードや毛布などを受け入れている団体もあります。
ボランティアの内容や条件、寄付できる物品などは団体によって異なりますので、必ず確認したうえで、必要とする支援をしましょう。
今回はねこの殺処分という重いテーマで、楽しいお話ではありませんでした。
しかし、命ある生き物をペットとして飼っている私たち人間にとって、目をそらしてはいけない重大な問題です。
これ以上不幸なねこが増えないようにするには、まず今飼っている愛猫を大切にすることが一番です。
そのうえで、もしできることがあるのなら、小さなことからでも始めてみてはいかがでしょうか。