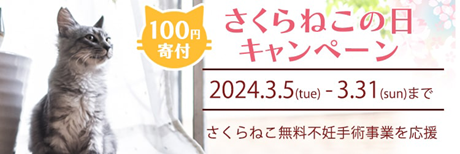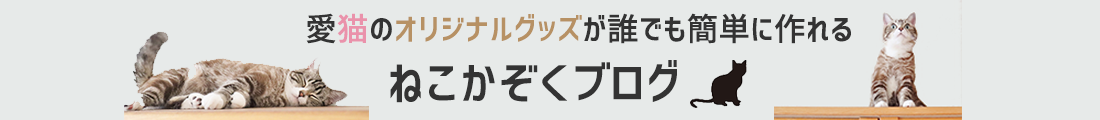
地域猫って何?さくら猫とは?地域猫との上手な関わり方について紹介

地域猫とは特定の飼い主がいない、街で見かけるねこの中でもその地域で協力して管理・お世話をされている、ねこのことです。
地域猫の中にはもともとは野良猫だったねこや、飼い主が育てきれずに野生に戻されてしまったねこがいます。
このようなねこを、地域住民が協力して、特定の場所や時間での餌やり、そしてトイレの設置などをして育てるのです。
この記事では、「さくら猫」についても解説していきます。
ねこかぞくでは、さくらねこ応援グッズの販売を通して、「さくら猫」の支援活動を推進しています。
さくらねこ応援グッズの販売1つにつき、100円をどうぶつ基金様に寄付し、さくらねこ不妊手術事業を応援しています。
詳しくは、以下のさくらねこ応援グッズ一覧ページをご確認ください。
さくらねこ応援グッズ一覧
目次
1.知っておきたい4タイプのねこ
∟1-1.地域猫
∟1-2.野良猫
∟1-3.迷い猫
∟1-4.飼い猫
∟1-5.地域猫と野良猫の違い
2.地域猫活動とは
∟2-1.適切なエサやり
∟2-2.不妊去勢
∟2-3.トイレの設置
∟2-4.地域の協力
3.TNR活動
∟3-1.TNR活動とは
∟3-2.さくらねことは
まとめ
1.知っておきたい4タイプのねこ

普段の生活の出くわすねこは、大きく4タイプに分けられます。
今回ご紹介している「地域猫」、「野良猫」、「迷い猫」、「飼い猫」です。
それぞれのねこが、どのように定義づけられたねこなのか、説明していきます。
1-1.地域猫
最近(2022年7月時点)公益社団法人ACジャパンCMにもなっていますので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
もともとは野良猫であったが、地域(街)で飼われているねこです。
飼われていると言っても特定の家や部屋で飼われている訳ではなく、その街の範囲内で生活しています。
住民の協力を得ながら、地域全体でお世話をされているねこです。
食事や排泄のお世話以外にも地域猫は、これ以上ねこが増えないようにするため、不妊去勢手術が行われます。
不妊去勢手術を終えたねこには、そのしるしとして耳をV字カットしたり、ピアスが付けて目印としています。
このV字カットした耳のことをさくらみみ、またはその猫のことを「さくらねこ」と呼びます。
施術されたねこは、地域でしっかりとお世話されており、みんなに可愛がられていることは言うまでもありません。
1-2.野良猫
飼い主がいない野生の猫のことを示します。
地域の方のエサやりや日常の鳴き声、そして発情期の鳴き声など、その地域のトラブルの原因となり得るねこです。
避妊手術をしていないので、野良猫は多くの子猫を、生む傾向があります。
そのため、野良猫はさらなる野良猫を生み出してしまうのです。
また日本にはねこに関しての法律がありません。
保護や捕獲することはできても、不当に殺処分はできないのです。
野良猫が多い地域では、野良猫と地域ではどう向き合っていくのか真剣に向き合う必要があります。
また地域で世話をする、あるいは個人で世話をすると決めたら、真っ先に病院で感染症の有無や健康状態を確認してください。
1-3.迷い猫
野良猫と違い、飼い主はいるねこです。
しかし、飼われている家から出てしまい見知らぬ土地で迷ってしまっている、ねこのことを言います。
自分の意思で逃げ出している訳ではなく、飼い主が見つけ出してあげられなければ、見つけ出すのが困難なねこです。
迷い猫は、普段は人間に飼われているため、いきなり野生で暮らしていくのは難しい猫です。
そのため、野生で生活している期間が長くなればなるほど、生きていくのが厳しい状態になってしまいます。
1-4.飼い猫
文字通り飼われているねこです。
外で飼われているねこもいますが、基本的には、お家で飼うことが推奨されています。
飼い猫の中には首輪をつけずに飼われているねこもいるので、逃げ出してしまったときは、結果的に迷い猫になってしまうこともあります。
1-5.地域猫と野良猫の違い
管理してくれる人がいるねこか、いないねこなのかの違いです。
運の良いねこは、地域猫として街全体でお世話をしてもらえます。
しかし、街で遭遇するほとんどのねこは、残念ながら野良猫であることが多いです。
2.地域猫活動とは

地域猫活動とは、その地域にいる野良猫を減らし、ねこにとっても住民にとっても住みやすい街にしていくための活動です。
トラブルの原因になり得る野良猫と、これから増える野良猫を減らすために不妊去勢手術を行い、ご飯やトイレのお世話までします。
具体的にはどのような活動なのかを紹介していきます。
2-1.適切なエサやり
野良猫にエサをあげなければ、自然と数は減っていくのではないかと、考える人もいるかもしれませんが、そうはいきません。
ゴミをあさったり、人が住んでいる近くで食べ物はないかと、探したりする行動が見られるようになります。
野良猫と共存し、地域猫としねこを、管理していくためには、特定のご飯を食べる場所を設ける必要があります。
ご飯の散らかしを片付けたり、異臭問題にならないように、当番を決めて定期的に掃除をするようにしましょう。
2-2.不妊去勢
不妊去勢手術をすることで、さらなる野良猫を生むことを防止できます。
街で見かける野良猫は、見た目はかわいらしいですが、どうしてもトラブルの原因になってしまう場合は多いです。
地域猫ちゃんに手術を行えば、望まれない命を増やさずに済むのです。
ねこは年間で数回、1回につき4~6頭の子猫を生みます。
それだけの数の野良猫を1年で管理する必要が無くなります。
自治体によっては、手術の際に助成金が出るところもあるので、まずは役所に相談してみるところから始めてみましょう。
2-3.トイレの設置
地域の決まった場所にねこのトイレを作って、住民で管理してあげましょう。
特定の場所があることで、異臭問題や糞尿被害を減少させられます。
家の前で、いたずらをされてしまい困っている地域住民がいると思いますが、そういう方も減っていきます。
猫除けの水の入ったペットボトルを置いている家もよく見かけることはありませんか
行く頻度は少ないかも知れませんが、その分地域内の他のおうちの前でいたずらをしているのです。
その中でも糞尿の被害は特に不快です。
トイレの設置は、効果的でしょう。
2-4.地域の協力
地域猫活動をするには、地域が主体となり活動していくほかありません。
住民の中には、ねこが好きで餌付けをしている人や実際に猫を飼っている人がいます。
しかし、猫が原因でストレスを感じている人など様々な人がいるはずです。
この様な状況下で住民同士が、現状を自分事として考えて活動し、問題を解決していくしかないのです。
猫に関する地域内での集まりが増えることで、今まで以上に、地域のコミュニケーションが活性化することにもつながるかもしれませんよ。
3.TNR活動
3-1.TNR活動とは
TNR活動とは、野良猫に対して「捕獲する(Trap)」「不妊去勢手術をする(Neuter)」「元の場所に戻す(Return)」これらを実施する活動のことで、頭文字をとってTNR活動と呼ばれています。
野良猫を捕まえて、人間と野良猫が共生するための適切な手術を施し、元の場所に返してあげているのです。
また、さくらねこ活動や、さくらねこTNRなどさまざまな呼ばれかたで親しまれています。
動物愛護団体が中心となり活性化してきている活動です。
繁殖を防止し、ねこの殺処分の減少、ねこを一代限りの命で全うしてもらうことを目的として活動しています。
3-2.さくらねことは
不妊去勢手術をすると、手術を行ったねこの耳先を、手術済みであることを示すためにカットします。
その猫のことを「さくらねこ」と言います。耳の形状が桜の花びらに似ているところに由来です。
たしかに、さくらねこの耳を見ると、本当に、桜の花びらのような形をしているので、初めて見るとびっくりすると思います。
ただ、手術が施されたねこが必ずしも耳をカットされている訳ではないので、注意してください。
ちなみに、雄猫は右の耳、雌猫は左の耳がカットされています。
耳のカットは、麻酔が聞いている不妊去勢手術の最中に行われるので、ねこたちは痛みを感じることはありませんので、安心してください。
この命名については2012年に石垣島で開催されたTNR活動の際に、石垣市長とどうぶつ基金理事長と雑誌「ねこ」の編集長が「さくらねこ」という呼称を決めたと言われています。
耳が桜の形をしているねこは、その地域にお世話をしてくれる人がいることを示してくれています。
さくらねこがさまざまな場所で今後、増えていってくれると嬉しいですね。
ねこかぞくでは、さくらねこ応援グッズの販売を通して、「さくら猫」の支援活動を推進しています。
さくらねこ応援グッズの販売1つにつき、100円をどうぶつ基金様に寄付し、さくらねこ不妊手術事業を応援しています。
詳しくは、以下のさくらねこ応援グッズ一覧ページをご確認ください。
さくらねこ応援グッズ一覧
まとめ

地域猫とは、地域でお世話をされているねこで、もともとは野良猫や飼育放棄されてしまったねこたちのことを言います。
野良猫との定義の違いが難しいところですが、飼い主がいないのが野良猫で、地域住民にお世話をしてもらっているねこが地域猫です。
野良猫のトラブルで困っている地区がありましたら、住民同士で話し合って地域猫にしてあげてはいかがでしょうか。
みんながストレスなく楽しく生活できるようになりますよ。