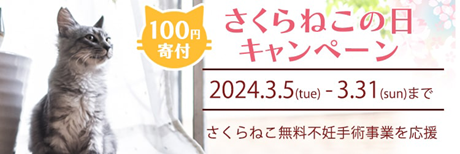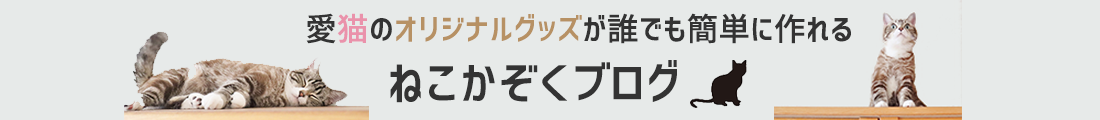
ねこに玉ねぎは絶対ダメ!猫が玉ねぎを食べてしまったときの症状と対応・対策

「ねこに玉ねぎは危険」ということを知っている人は多いと思います。
でも、玉ねぎのなにがどう危険なのか、ねこが食べてしまったときにどんな症状があらわれるのか、というところまで理解している人はほとんどいないでしょう。
今回は、ねこの玉ねぎ中毒の危険性やあらわれる症状、また万一の際の対処法についても解説していきます。
「猫 玉ねぎ」の目次
1.ねこに玉ねぎを与えてはいけない理由
∟1-1.ねこが中毒を起こす成分が含まれている
∟1-2.玉ねぎを加熱しても中毒成分はなくならない
∟1-3.玉ねぎ中毒の原因は玉ねぎだけじゃない
2.玉ねぎ中毒の症状
∟2-1.玉ねぎ中毒のおもな症状は溶血性貧血
∟2-2.ねこが玉ねぎ中毒を起こす摂取量と致死量
∟2-3.ねこが玉ねぎを食べてしまったらすぐに病院へ
3.ねこを玉ねぎ中毒から守るためにできること
まとめ
1.ねこに玉ねぎを与えてはいけない理由

ねこにとって玉ねぎはとても危険な中毒症状を起こす食べ物です。
個体差が大きいのではっきりしたことは言えませんが、ねこによっては小さなかけらを食べただけ、あるいは数回舐めただけでも症状があらわれたケースが報告されています。
人間にはごくありふれた野菜でしかない玉ねぎが、ねこにはどんなふうに危険なのかを知っておきましょう。
1-1.ねこが中毒を起こす成分が含まれている
玉ねぎには、ねこが中毒を起こす「有機チオ硫酸化合物」という成分が含まれています。
この有機チオ硫酸化合物をねこが摂取すると血液中の赤血球が壊され、溶血性貧血や血尿、急性腎障害などを引き起こします。
これら玉ねぎが原因で起こる、さまざまな機能障害をひとまとめにして「玉ねぎ中毒」と呼んでいます。
1-2.玉ねぎを加熱しても中毒成分はなくならない
有機チオ硫酸化合物は加熱しても分解されないため、生でも調理済みでも中毒を引き起こします。
しかも、煮込むことで成分が溶け出しますから、できあがった料理を見ただけでは安全かどうかを判断できません。
たとえば、みじん切りにした玉ねぎを使うハンバーグ、煮溶かしてしまうカレーなど、自分で料理をする人なら玉ねぎを使うことは知っているでしょうが、あまり料理をされない人や食べる専門の人にはわからないかもしれません。
煮込んだあと材料を取りのぞくラーメンのスープともなると、ねぎ類が使われているかどうかを判別するのはかなり難しいでしょう。
ようするに、人間が食べる料理全般が玉ねぎ中毒を引き起こす可能性があると考えたほうが手っ取り早いといえます。
つまり、事故を防ぐためには、日ごろから人間の食べものを与えないようにするのがいちばん確実なのです。
1-3.玉ねぎ中毒の原因は玉ねぎだけじゃない
一般に「玉ねぎ中毒」と呼ばれていることもあって、危ないのは玉ねぎだけだと思っている人もいるようです。
しかし、実際には玉ねぎだけでなく、長ねぎ、ニラ、ニンニクなどのねぎ類全般が対象となります。
以下に食卓に欠かせない野菜のうち、ねぎ類に分類されているものをまとめておきます。
- ・長ねぎ
- ・あさつき
- ・わけぎ
- ・ニラ
- ・ニンニク
- ・らっきょう
- ・ユリ根
- ・エシャロット
これらには玉ねぎ同様に「有機チオ硫酸化合物」が含まれていますので、ねこにいたずらされたりしないよう、扱いには充分に注意しましょう。
2.玉ねぎ中毒の症状

2-1.玉ねぎ中毒のおもな症状は溶血性貧血
玉ねぎ中毒の症状として代表的なものが溶血性貧血です。
ねこが玉ねぎ中毒を起こすと、まだ寿命を迎えていない赤血球が過剰に壊され、その成分が血液中に溶け出します。
これを「溶血」といいます。この溶血によって引き起こされる貧血が「溶血性貧血」です。
溶血性貧血になると、全身に酸素を運ぶ赤血球が減少するので、体の各部で酸素不足におちいってしまいます。
初期的な症状としてあらわれるのは、「元気がない」「食欲不振」「発熱」「吐き気・嘔吐」「下痢」などです。
そのほか、玉ねぎ中毒の症状としてよく知られているものには次のようなものがあります。
- ・粘膜や白目が黄色になる(黄疸)
- ・赤茶色の尿が出る
- ・呼吸が速い
- ・脈が速い
- ・震え・痙攣
- ・意識障害
玉ねぎ中毒は摂取してから症状があらわれるまでにタイムラグがあり、12時間〜数日後に症状が出るといわれています。
食べてすぐには問題がないように見えても忘れたころに症状があらわれることがあるので注意が必要です。
2-2.ねこが玉ねぎ中毒を起こす摂取量と致死量
中毒症状があらわれるとされている摂取量は、ねこの体重1kgあたり約5gです。
大人のねこなら体重は3〜5kgですから、15〜25g程度摂取すると中毒を起こす可能性があるといえます。
スーパーで買える中サイズの玉ねぎ(横径が7〜8cm程度)のものがだいたい200g前後ですから、おおざっぱに10分の1前後です。
致死量は体重1kgあたり15〜20gといわれています。
計算上は大人のねこが45〜100g程度食べれば死に至る可能性があることになります。
中サイズの玉ねぎにすると4分の1から半分程度です。
しかし、この数字は単なる目安でしかありません。
中毒を起こす量、致死量ともにかなり大きな個体差があって、どこまでが安全なのかまったくわからないのです。
また、ねこは有機チオ硫酸化合物への感受性がほかの動物の数倍ともいわれていて、ひと口かじっただけで重い中毒症状が出た例もあるそうですから油断はできません。
2-3.ねこが玉ねぎを食べてしまったらすぐに病院へ
もし、愛猫が玉ねぎを食べてしまったとしても、家でできることはなにもありません。
すぐに動物病院に連れていきましょう。
食べてから2時間程度以内であれば、薬を使って吐かせることができます。
吸収する量が少なければ少ないほど症状を軽減できる可能性がありますから、処置が早いほどリスクも抑えられるのです。
吐いた場合も食べた分すべてが出たとはかぎりませんし、汁気だけでも危険性は残ります。
ですので、猫が玉ねぎを食べてしまったことに気づいたら必ず受診しましょう。
また、玉ねぎ中毒は時間勝負でもありますので、夜間や休日であっても救急で診てもらえる動物病院に連れていくようにしてください。
なお、受診時には以下のことを伝えられるようにメモしておくことをおすすめします。
あるいはスマートフォンなどで撮影しておいてもよいでしょう。
- ・何時ごろ
- ・なにを食べたか
- ・食べた量
- ・どんな症状が出ているか(時間、頻度、回数なども)
なにをどれぐらい食べたかについては、ねこが食べた玉ねぎなどの現物を持参してもよいでしょう。
もし、嘔吐や下痢といった症状がある場合も写真に撮っておく、もしくは持参します。
ねこが玉ねぎを食べたかどうか分からないというときも獣医師に相談して指示を仰ぎましょう。
玉ねぎ中毒は命にかかわりますから、安易な自己判断だけは絶対に避けてください。
3.ねこを玉ねぎ中毒から守るためにできること

愛猫を玉ねぎ中毒から確実に守るためには、玉ねぎをはじめとするねぎ類に近づけないことです。
- ・人間の食べものを与えない、興味を持たせない
- ・ねこの手が届く場所に置きっ放しにしない
- ・ねぎ類を触ったらしっかりと手を洗う
- ・調理中はキッチンにねこを入れない
- ・においが漏れにくい蓋付きのゴミ箱に変える
玉ねぎをはじめとするねぎ類は食卓には欠かせない食材ですし、細かく刻んだりすり下ろしたり、煮込んだあと取りのぞいたりすることもあります。
そのため、できあがった料理を見ただけではねぎ類が使われているかどうかわからないケースも多いです。
だからこそ、事故を避けるためにも人間の食べものを与えない、興味を持たせないことが大切です。
ねこが出入りできる場所にねぎ類を放置しない、においの漏れにくいゴミ箱を使って生ゴミに興味を持たせないといった対策をして、ねこがねぎ類に触れないようにしっかりと管理しましょう。
また、調理中に玉ねぎなどのかけらや皮を落とすこともあるでしょうから、食事の支度をしているあいだはキッチンにねこを入れないような工夫も必要です。
ねぎ類を触ったあとはにおいが残らないようにしっかりと手を洗うこともお忘れなく。
「猫 玉ねぎ」のまとめ
玉ねぎをはじめとするねぎ類は人間にとってはなくてはならない食材ですが、ねこが玉ねぎを食べると中毒を起こし死に至ることもあります。
有毒成分である「有機チオ硫酸化合物」は加熱しても破壊されず、煮汁にも染み出します。
そのため、ねぎ類自体はもちろん、汁やいっしょに料理した食材も与えてはいけません。
また、摂取量は個体差が大きく、ひと口かじっただけで中毒を起こす可能性もありますので油断はできません。
取り扱いには十分に注意しましょう。